
こんにちは、大学受験コンサルタントの田中です。
大学受験を突破するために、予備校や塾に通うことは受験生の中で常識となっています。しかし、予備校と塾には、どのような違いがあるかご存じでしょうか?正しい大学受験対策をするために、両者の違いとメリット・デメリットについて知っておきましょう。
目次 [非表示]
予備校と塾の違いとは?
大学受験のための予備校、塾、どちらも同じようなものと思っていませんか?多くの高校生は、「今日は塾の日」という風に言うかもしれませんね。一方で浪人生は、「塾に通う」ではなく「予備校に通う」という言い方をしますから、なんとなく対象者によって大学受験対策ができる場所が違う、というイメージを持っている人も多いのかもしれません。
結論から言いましょう
予備校と塾の違いとは、「指導形式と目的」にあります。
塾は学校と同様に、先生と生徒との「授業形式」で指導を行います。問題を解答させたり、生徒の質問に答えたりすることから、足りない学力を補うのが塾の大きな特徴です。
一方、予備校は講師が一方的に解説をする「講義形式」であり、受け身の状態で聞くことになります。「大学受験の合格」に目的を絞っており、大学受験対策が効率よくできるのが予備校の特徴です。
もちろん、どちらもできる予備校・塾もありますから、この分け方は必ずしもすべてに共通するわけではないのですが、「指導形式」や「目的」について注目してみてもよいでしょう。
授業形式
予備校の場合
予備校では、基本的に大人数を対象にした講義形式の授業が主流です。一流の講師が一度に多くの生徒に教えるため、大学の講義のような雰囲気があります。板書を中心に進行し、生徒は受動的に学ぶことが多いです。そのため、自分で復習や理解を深める姿勢が求められます。
塾の場合
塾では少人数制や個別指導が一般的です。生徒一人ひとりの学力に応じたカリキュラムを組むことが多く、個別のニーズに対応しやすいのが特徴です。双方向型の授業が多いため、質問しやすい環境が整っています。生徒の理解度に合わせた柔軟な指導が可能です。
講師の質
予備校の場合
予備校の講師は、カリスマ性や実績を持つプロフェッショナルが多いです。全国規模で有名な講師が教材を作成し、難関大学の入試に特化した授業を展開します。ただし、生徒一人ひとりに直接指導する機会は少ないため、自主学習が重要になります。
塾の場合
塾の講師は、地域密着型で生徒一人ひとりに寄り添う指導を重視します。大学生や現役教師が務めることが多く、進学先や試験内容に関する具体的なアドバイスを受けやすいです。生徒の性格や学力を考慮した親身なサポートが期待できます。
講師との距離感
予備校の場合
予備校では、生徒と講師の距離は比較的遠く、直接のやり取りは少ないです。質問がある場合、講師に直接話しかける機会は少なく、チューター制度や質問専用の時間を利用することが一般的です。自主性が重視される環境といえます。
塾の場合
塾では、生徒と講師の距離が非常に近いのが特徴です。少人数制や個別指導の環境で、質問や相談がしやすく、生徒の悩みにも丁寧に応えてくれます。講師が学習だけでなく生活面でもアドバイスをすることも珍しくありません。
受験対策
予備校の場合
予備校は、難関大学を目指す生徒向けのカリキュラムが整っています。過去問の分析や入試傾向の研究に基づいた授業が行われ、最新の受験情報を提供します。一流の講師陣による高度な指導で、学力の飛躍的な向上を目指せます。
塾の場合
塾では、生徒一人ひとりの目標に応じた受験対策が可能です。学校の定期試験対策から推薦入試まで、幅広いサポートを提供します。柔軟なスケジュールで生徒のペースに合わせた学習を重視し、細やかな指導で基礎学力を固めます。
時間割
予備校の場合
予備校の時間割は決まったスケジュールに従います。多くの場合、コースや科目ごとに固定された時間割が設定されており、授業は集団講義形式で行われます。時間の融通が利かない場合もありますが、計画的な学習が可能です。
塾の場合
塾では、生徒の都合に合わせた柔軟な時間割を組むことが可能です。特に個別指導の場合、平日や休日の夕方以降に授業を組み込むことが一般的です。部活動や他のスケジュールと両立しやすい点がメリットです。
費用
予備校の場合
予備校は、講師の質や提供される教材の充実度が高いため、費用が比較的高額になる傾向があります。年間で数十万円以上の費用がかかることもありますが、難関大学を目指す生徒にとって価値のある投資といえるでしょう。
塾の場合
塾は、規模や形式によって費用が異なります。個別指導や少人数制では費用が高くなる場合がありますが、大手塾の集団指導なら比較的リーズナブルです。地域密着型の塾では費用が抑えられる場合も多いです。
予備校と塾にそれぞれに向く人とは?
予備校と塾はそれぞれ異なる特徴があります。それぞれどのような人に向いているのか解説します。
予備校が向いている人
予備校は、難関大学や特定の大学学部を目指す生徒に向いています。学力の底上げや高度な問題への対応が必要な生徒、また集団の中で自主的に学べる人に適しています。全国規模の試験対策や模試を活用したい場合も予備校が適切です。
塾が向いている人
塾は、学校の定期試験対策や基礎学力の向上を目指す生徒に向いています。個別のカリキュラムや柔軟なスケジュールが必要な生徒、講師との距離感が近い環境で学びたい生徒に適しています。
予備校のメリット・デメリット
予備校には以下のメリットとデメリットがあります。予備校と塾のどちらに行くか悩んでいる受験生は、ぜひ参考にしてみてください。
予備校のメリット
予備校ならではのメリットは、以下の3つが挙げられます。
実践的な入試対策ができる
大学受験合格に重点を置いているため、志望校や学部の入試傾向を踏まえた実践的なカリキュラムを受けられるのが大きなメリットでしょう。大学受験に必要な学力を効率よくアップできるので、志望校の合格がより現実的になるのが予備校ならではの魅力です。
夏期講習や冬期講習、直前講習など、必要なタイミングで特別講座が準備されているので、志望大学や今の学力に合わせて、長期休暇中も効果的な学習が可能になります。
勉強に集中できる環境の提供
予備校には、無料の赤本貸し出しサービスがあったり、自由に使用できる自習室が設置されていたりすることが多くあります。勉強に集中できる環境を与えてくれるので、自宅では気が散るという受験生にとって大きなメリットとなるでしょう。また、同じ志望校を目指す仲間とも出会え、友に切磋琢磨できるので、モチベーション向上の効果も期待できます。
↓↓?自習室をフル活用して合格した先輩の声↓↓

大学の入試情報が豊富
大学入試システムは近年多様化しており、それに伴い複雑化しています。近年では独自の受験システムを実施する大学も増えています。大学の入試情報が豊富にある予備校なら、詳しい情報を入手することができます。学校の進路指導では得られない最新の情報があるのは、予備校ならではのメリットと言えるでしょう。
また、大手3大予備校(河合塾、駿台予備学校、代々木ゼミナール)は、国の認可を受けた学校法人です。これらの予備校に通う生徒は学生扱いになり、電車やバスの定期購入時に学割が利くのもメリットと言えるでしょう。過去に法律が改正され、学校法人の認可基準が厳しくなったため、古くからある3大予備校以外は学校法人の認可を受けることが難しいのが現状です。
進路指導も重要
志望大学が決まっている場合にも、どの入試方式で受験するのか?選択科目はどうするか?など、実は色々と考えなければいけないことがあります。もしも志望大学が決まっていないのであれば、勉強したいことは何学部なのか、その学部がある大学はどこで、偏差値はどのくらいの幅があるのか、などなどさらに調べることも多くあります。
そこで頼りになるのが、大学受験のプロである「受験コンサルタント」という存在です。予備校によってそうしたサポーターが付かない場合もありますから、大学入試情報を集めるだけでなく、戦略的に利用できるように大学受験予備校の進路指導のサポートを活用するとよいでしょう。そうすることで、効果的に効率的に受験に臨むことができます。
?受験コンサルタントの受験戦略アドバイス

予備校のデメリット
予備校のデメリットと言える点は以下の3つがあります。
大人数クラスの場合、自主性が必要

予備校は、講義を大勢の受験生と一緒に受けるため、個人の学力に合わせることはありません。大きな教室で大勢の生徒が授業を受けるというスタイルの四b校であれば講義の最中に質問することはなかなか難しいでしょう。質問制度がある予備校も多いのですが、実際に先生に質問に行ったり、日々の予習復習をしたりと言ったことは、生徒一人ひとりのの自主性に委ねられる部分が大きいのがデメリットと言えます。
予備校に行くだけで勉強した気になってしまう

予備校は実践的な講義と豊富な受験情報を聞くことができますが、予備校に通っていることで「勉強した気になる」受験生も少なくありません。勉強は聞いて理解するだけでは実力に結びつかず、解けるまで自分で勉強する必要があります。勉強した気になると予備校に通っても実力が身に付かず、問題が解けないという結果になるので注意が必要です。
しかも55段階の進捗状況は、常にWEBページでチェックできます。どのSTEPまで行ったか、目標段位まであとどのくらいか、ペースが適切か、といったスケジュール管理はもちろんですが、
何点で合格したか?同じ志望校の先輩は、同時期のどの段まで進んでいたか?
なども詳しくチェックすることができるんです。
55ナビシステムで、データを分析してあなたの学習をしっかり管理するから「やったつもり」「わかったつもり」を残しません。
進路指導がない
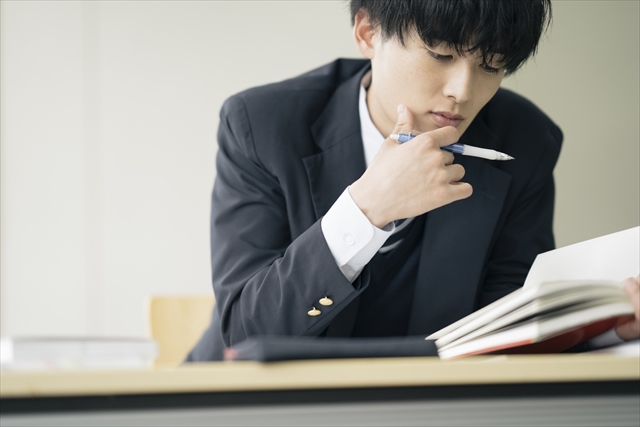
予備校では、先生=講師は学習の内容について教えてくれる人。講師の先生は大学の進路相談は基本的に行っていません。より大学合格に直結した学習を行うためには、志望校に適応したカリキュラムを組む必要があるので、志望校が決まってから予備校に通うのが望ましいでしょう。
さらに、「進路指導ガイダンス」と呼ばれるサポート体制を敷いており、1年間の勉強の仕方や出願校決定ガイダンス、共通テストガイダンスなど、1年を通じて充実したサポートを受けられます。
塾のメリット・デメリット
予備校にはない、塾ならではのメリットとデメリットは以下の通りです。予備校との違いを知ることで、自分に合った大学受験対策ができるでしょう。
塾のメリット
塾のメリットは、以下の2つが挙げられます。
個別指導が可能
塾は先生と生徒とマンツーマンの個別指導ができることで、苦手科目の強化と基礎力アップができるのが最大のメリットでしょう。自分の学力に合わせたカリキュラムを組める上に、分からない部分はすぐに質問できるのも塾ならではの魅力です。
進路指導ができる
先生との距離が近いことから、生徒の学力を把握した手厚い進路指導が可能です。志望校をなかなか決められない受験生は、先生と相談しながら志望校を絞れる塾が向いているでしょう。
塾のデメリット
塾のデメリットと言える点は、以下の2つがあります。
アルバイトの講師の場合もある
予備校は入試対策を研究している、いわば大学受験指導のプロと言えます。経験豊富な講師が在籍する塾もありますが、一般の社会人や大学生がアルバイトとして講師を勤めている塾も少なくないようです。指導力は受験生の実力向上に直結するので、塾を選ぶ際は体験入学するのが望ましいでしょう。
自習室のある塾は少ない
予備校のように自習室を備えている塾は少なく、塾以外は自宅などで勉強する必要があります。自宅では勉強するのが難しい受験生は、自分で勉強しやすい場所を探さなければなりません。
まとめ:予備校と塾のメリット・デメリットを理解しておこう

予備校と塾の違いと、メリット・デメリットについてご紹介しました。それぞれに違いはありますが、自分にとってどちらが合うかを見極めることが重要です。
| メリット | デメリット | |
| 予備校 | ・実践的な大学受験対策ができる ・大学入試の情報が豊富にある ・勉強に集中できる環境に身を置ける | ・志望校を決めておく必要がある ・自主的な学習が必要不可欠 ・講師は勉強や進路の相談を受け付けていない ※四谷学院の場合はプロの受験コンサルタントが学習相談に乗ります |
| 塾 | ・基礎力と苦手科目の克服に最適 ※四谷学院は基礎からしっかり学べるので苦手科目もしっかり対策すれば克服が可能 ・分からない部分をすぐに質問できる ・進路相談で志望校を後から決められる | ・アルバイトの先生の場合は指導力に不安がある ・塾以外で勉強しやすい環境を探す必要がある |




