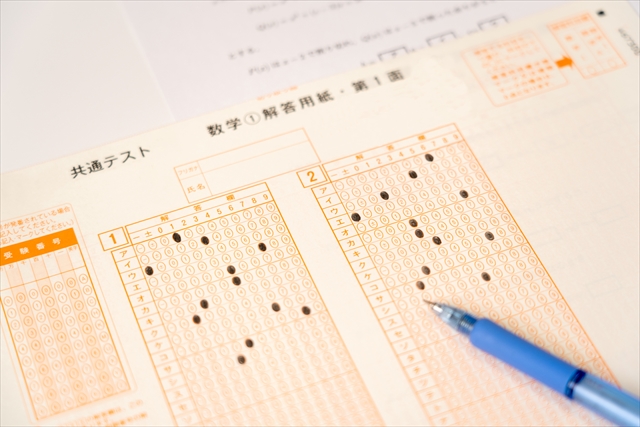このページでは、令和7年度(2025年度)の大学入学共通テスト「世界史」の出題について解説します。
目次
新課程
新「歴史総合、世界史探究」
大学入試センターが公表していた試作問題と同じく大問数は5でした。
解答番号数は33から32に減少しています。
試作問題と同様、第1問が歴史総合、第2問以降が世界史探究からの出題でした。
出題傾向は試作問題から変更がなく、資料・設問文・会話文の読み取りを要する問題が多数出題されました。
中には文章を読まない、もしくは一部しか読まずに断定してしまうと誤答になってしまう問題もあり、文章には一通り目を通す必要がありました。
第1問では日本史分野からの出題もありましたが、試作問題と同様に中学歴史レベルの問題となっていました。

第1問
歴史総合からの出題で、問3・問4・問8を根拠も持って解答するためには日本史分野の知識が必要でした。
問3は1858年に日米修好通商条約が締結されていたことと、諸外国との条約締結が幕府主導で行われたことを理解している必要がありました。
問4のグラフから読み取れることに関して述べた文については、日本の帝国議会の開設が1890年の出来事であったことを知っていれば、根拠を持って解答することができました。
問8は男女雇用機会均等法の制定が1986年であったことを理解していれば解答することができましたが、世界史選択者には少し難しい問題だったと思います。
その他、問4の綿糸の生産量に関して述べた文について解答するためには、力織機が布を織る装置、紡績機が綿糸を生産する装置であったことを理解しておく必要があり、機械名と制作者名を暗記するだけにとどまっていた受験生には解答できない問題でした。
第2問
試作問題と同様に都市をテーマにした大問でした。
問6では試作問題に見られたような地図の読み取りが出題されていましたが、地図を見て知識と照らし合わせれば、解答できたことでしょう。
その他、問3は1924年にレーニンにちなんでペトログラードから改称されていた「レニングラード」が、1991年に再び「サンクト=ペテルブルク」に改称されていたことを知っておく必要があり、少し細かい知識を要求する問題でした。
また問5を解答するためには、ラタナコーシン朝が成立したおおよその時期を理解しておく必要があり、周辺地域史まで十分に対策できていたかどうかで明暗が分かれる問題でした。
第3問
資料をテーマにした大問でした。
資料や説明文を読み取らなければ解答できない設問がいくつかあり、そのような設問では解答に必要な箇所を素早く読み取ることが必要でした。
このような問題に対応するためには、日頃から過去問題等を通じて、資料問題の形式に慣れておく必要があります。
問7では資料4が書かれた時期について問われました。
1つ目の項目のみを見て、「8か国連合軍が都を占領した」から義和団戦争の時期と判断してしまった受験生がいたかもしれませんが、次の項目にそこから30年とあるのでZを選択する必要がありました。
このように文章を読まない、もしくは一部しか読まずに断定してしまうと誤答になってしまう問題もあります。
文章には一通り目を通す必要があり、そのために文章を素早く正確に読む力が必要になります。
第4問
諸地域の結びつきをテーマにした大問でした。
問1や問2ではグラフに関する問題が出題されていましたが、知識と照らし合わせてしっかりと読み取れば十分に対応できる問題でした。
第5問
政治権力と食料事情をテーマにした問題でした。
問5では試作問題と同様、大問の主題を問う問題が出題されましたが、各設問を解くなかで資料をしっかりと読み取れていれば、解答できたことでしょう。
問4では統計資料に関する問題が出題されましたが、細かい計算をせずとも解答できる問題になっていました。
旧課程
旧「世界史B」
昨年度から大問数が4から5に増加しました。
解答番号数は昨年度同様、33でした。
出題傾向は昨年度から変更がなく、資料・設問文・会話文の読み取りを要する問題が多数出題されました。
中には文章を読まない、もしくは一部しか読まずに断定してしまうと誤答になってしまう問題もあり、文章には一通り目を通す必要がありました。
ただし、3つ以上の資料を読み取らせる設問がなくなり、資料自体も読みやすいものが多かったため、例年よりも取り組みやすかったことでしょう。

第1問
歴史的な文物をテーマにした大問でした。
資料・説明文・会話文を読み取らなければ解答できない設問がいくつかあり、そのような設問では解答に必要な箇所を素早く読み取ることが必要でした。
このような問題に対応するために、日頃から過去問題等を通じて、資料問題の形式に慣れておく必要があります。
問3の尾形さんのメモについて、ギリシアの文化がアケメネス朝ペルシアの文化の影響を受けていたという話を聞いたことがないとして不適と判断してしまった受験生がいるかもしれませんが、会話文を読むと影響を受けていたことが分かります。
安易に断定せず、資料・説明文・会話文に目を通してから解答することが必要になります。
また、問2ではアケメネス朝ペルシアの最大領域を問う問題が出題されましたが、このような問題に対応するためにも資料集等で地図を確認しておくようにしましょう。
第2問
支配と従属をテーマにした大問でした。
第1問と同様、資料・説明文を読み取る必要がある設問が含まれていましたが、しっかりと読めていれば問題なかったでしょう。
第3問
帝国の制度や政策をテーマにした大問でした。
問4ではグラフに関する問題が出題されました。
空欄オについては、グラフから貿易収支がマイナスになっていることを読み取れれば、輸出額よりも輸入額の方が多いと判断できました。
問7では統計資料に関する問題が出題されましたが、複雑な計算は必要とせず、各出来事が示す時期を理解できていれば、十分に対応できる問題でした。
第4問
植民地と宗主国の関係をテーマにした大問でした。
問1では地図問題が出題されましたが、普段から地図を意識して学習していた受験生は問題なく解答できたことでしょう。
第5問
近現代のアメリカ合衆国をテーマにした大問でした。
問2・問5・問6は現代史からの出題で、問2は21世紀の出来事からの出題でした。
現代史は対策がおろそかになってしまう受験生が多い分野ですので、しっかりと学習しておきましょう。
旧「世界史A」
昨年度から大問数が5から4に減少しました。
解答番号数は昨年度同様に30でした。
出題傾向は昨年度から変更がなく、資料・設問文・会話文の読み取りを要する問題が多数出題されました。
難易度も例年通りでした。
今年度も、単純に用語名を覚えているだけでは太刀打ちできない問題が多数みられ、用語の意味・内容や、各時代・地域の歴史の流れ・社会情勢までしっかりと理解しておく必要がありました。

第1問
図像や銅像をテーマにした大問でした。
説明文や会話文を読み取らなければ解答できない設問がいくつかあり、そのような設問では解答に必要な箇所を素早く読み取ることが必要でした。
このような問題に対応するためには、日頃から過去問題等を通じて、資料問題の形式に慣れておく必要があります。
第2問
近代以降の国内政治の変容・推移をテーマにした大問でした。
グラフに関する問題が出題されていましたが、知識と照らし合わせてしっかりと読み取れば十分に対応できる問題でした。
第3問
女性をテーマにした大問でした。
問6の山田さんのメモについては、資料を読み取って解答する必要がありましたが、資料1の意図を正しく汲み取る必要があり、読解力が必要でした。
第4問
民族をテーマにした大問でした。
問7では地図問題が出題されましたが、このような問題に対応するために、普段から地図を意識して学習する必要があります。
問8では統計資料に関する問題が出題されましたが、計算自体は複雑なものではありませんでした。
新高3生・高2生へのアドバイス
今年度の「歴史総合、世界史探究」の第1問は中学歴史レベルの日本史分野の知識があれば、解答することができる問題となっていましたが、「歴史総合、日本史探究」の第1問では世界史分野からの出題がかなり見られたため、次年度以降は日本史分野からの出題が増えるかもしれません。
これまでに学習した歴史総合 日本史分野の内容をしっかりと確認しておきましょう。
また従来の「世界史B」と同様、資料・設問文・会話文の読み取りを要する問題が多数出題されました。
次年度以降もこの傾向は続いていくと考えられますので、過去問題等を通じて、独特な問題形式に慣れておきましょう。
文章を読まない、もしくは一部しか読まずに断定してしまうと誤答になってしまう問題もあります。
文章には一通り目を通す必要があり、そのために素早くかつ正確に読む力をつけましょう。
今年度も、単純に用語名を覚えているだけでは太刀打ちできない問題が多数みられました。
用語の意味・内容や、各時代・地域の歴史の流れ・社会情勢までしっかりと理解しておきましょう。
世界史の共通テスト対策