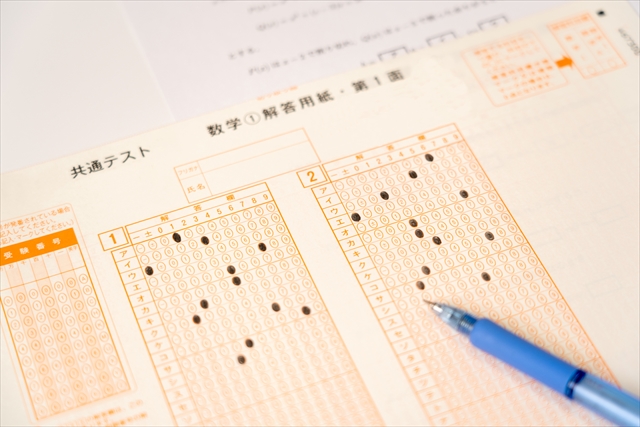このページでは、令和7年度(2025年度)の大学入学共通テスト「日本史」の出題について解説します。
目次
新課程
新「歴史総合、日本史探究」
2025年の共通テスト「歴史総合、日本史探究」では、2024年の共通テスト日本史Bよりも設問数が1問増加し、6つの大問すべてが高校生の探究活動を題材にしたものとなりました。
歴史総合では試作問題とは異なり、日本史の知識だけでは対応できない問題も出題されました。
日本史探究の分野では、2023年、2024年の日本史Bで出題されていた8択の問題は姿を消し、多様な資料が出題されました。
また、時期判断がカギを握る問題も多く出題され、受験生の理解の深さや思考力が問われました。

第1問
歴史上の「境界」をテーマにした、「歴史総合」の第1問と共通の問題でした。
試作問題では、ほぼ日本史の知識のみで対応できる問題で構成されていましたが、問3や問7は日本史の知識だけでは対応しにくく、歴史総合の学習の成果が問われました。
第2問
菓子をテーマにして、古代~近代について総合的に出題されました。
問4の正誤問題は、下線部の「中世の禅宗寺院」という問題設定を見逃してしまうと、選択に悩んでしまったかもしれません。
問5は知識だけでなく会話文をヒントにしながら、解答する必要がありました。
このタイプの問題は共通テストでは頻出となっています。
第3問
太宰府を中心に古代の外交、文化について出題されました。
問1、問3、問5ではこれまでの日本史Bには見られない出題形式となっており、戸惑った受験生もいたかもしれません。
しかし、いずれも「何世紀に何が起きたのか」という時期把握ができていれば、解答できるようになっていました。
第4問
中世の武士をテーマに、中世について総合的に出題されました。
問3のイや問4など、一部難しく感じた受験生もいたかもしれませんが、消去法によって解答が導けるようになっており、知っている知識を活用できたかがポイントになりました。
第5問
近世の村をテーマに、近世の政治や社会に関する問題が出題されました。
問3の年代整序問題は、センター試験時代から頻出の形式ですが、今回は誰が行った政策なのかを考えると解きやすい問題でした。
また問4、問5はメモやグラフを活用すれば、消去法も有効でした。
第6問
松本清張の年譜をテーマに、近現代の政治、経済、文化について出題されました。
いずれの問題も、時期判断がポイントになっていました。
問1の「資料1から読み取れる内容」では、資料中の「総督府」に惑わされず、資料1が韓国併合以前のものであることに注意する必要がありました。
また問4では、破壊活動防止法が制定された理由・背景がわかっていれば、時期判断も容易だったでしょう。
旧課程
旧「日本史B」
2025年の共通テスト日本史Bは、昨年と同じ大問数・設問数で構成されていました。
史料、絵画資料、統計など多様な資料を用いた出題が目立ち、持っている知識をもとに、必要な情報を見抜き、判断することが求められました。
また年代整序問題が減少した一方で、時期の特定を必要とする設問も多くみられ、単なる用語の暗記ではなく歴史的事象の背景や流れを含めた深い理解が必要とされました。

第1問
馬をテーマに古代~近代について総合的に出題されました。
問2では「牧」について問われ、初めて聞く用語に混乱した受験生もいたかもしれませんが、表や資料の読解で解答できるようになっていました。
また問6は表や年表など、大問全体の資料を活用する必要がありました。
第2問
古代の日本と新羅を中心とする東アジアの国々との関係についての出題でした。
大問をとおして史料や年表の読み取りが必要な部分と、知識が求められる部分のバランスがとられていました。
問5では会話文、史料1、史料2、表を活用して判断しなければならなかったので、時間がかかってしまった受験生もいたかもしれません。
第3問
「中世の石材利用と宗教」をテーマに、中世の社会経済、文化について出題されました。
苦手にする人が多い分野でもあることから、苦戦した受験生もいたと思います。
問3は史料内の用語と同じ意味の語句を選択する、という今までにない形式の問題が見られました。
また問5では知識を前提としながら、図と表から丁寧に情報を読み取ることが求められました。
第4問
「江戸時代の人命をめぐる幕府・諸藩の政治」をテーマにした出題でした。
全体としては教科書レベルの知識がシンプルに問われる問題が多く、史料も比較的読みやすいものだったので、しっかり得点していきたいところでした。
ただ問3のⅠはヒントが少なく、時代の特定に悩んだ受験生もいたと思われます。
第5問
明治時代の鉄道遺跡と日本の近代化をテーマにして、幕末から明治時代の社会経済を中心とした出題となりました。
問2、問4は史料やメモ、表の読み取りが求められましたが、注を含めて丁寧に読み取れば、比較的取り組みやすい問題でした。
第6問
近現代の日本の産業発達と環境問題をテーマにして、近現代の社会経済を中心に出題されました。
問2や問4では歴史的事象の流れや時期の理解が求められました。
また問6では公害問題が発生した場所についても把握しておく必要がありました。
旧「日本史A」
2025年の共通テスト日本史Aでは、知識問題、史料問題、年代整序問題など、これまでの共通テストで頻出の形式がバランスよく出題されていました。
史料問題では、初めて見る史料に戸惑った受験生もいるかもしれませんが、難易度の高いものではなく、落ち着いて読み取り、持っている知識と組み合わせて考察することで正解にたどり着けるようになっていました。
また日本史探究、日本史Bと共通して、一問一答形式の用語の暗記だけでは答えにくい、歴史的事象の意味や背景を踏まえた出題となっており、歴史を多角的に理解することが求められました。

第1問
『自分史』という冊子をテーマに、明治初期から占領期について総合的に出題されました。
史料読み取り問題、組み合わせの問題、年代整序問題など典型的な問題が出題され、過去問演習をしていた受験生にとっては解きやすい問題になっていたと思います。
問6、問7ではソ連による占領の様子が出題されるという点で珍しさはありましたが、シンプルな史料読解や基本的な知識で対応できる問題でした。
第2問
明治時代の鉄道遺跡と日本の近代化をテーマにして、幕末から明治時代の社会経済を中心とした出題となりました。
問2、問4は史料やメモ、表の読み取りが求められましたが、注を含めて丁寧に読み取れば、比較的取り組みやすい問題でした。
第3問
明治・大正期の日本と東アジアの関係をテーマにして、対外関係が中心に出題されました。
問3ではメモをもとにグラフの推移を考える、新しい形式の問題が出題されましたが、落ち着いてメモを読み取れば易しい問題だったでしょう。
問7では外国の料理の受容の仕方に関するユニークな資料が出され、当時の日本人の外国へのまなざしを読み取る問題になっていました。
第4問
近現代の日本の産業発達と環境問題をテーマにして、近現代の社会経済が中心に出題されました。
問2や問4では歴史的事象の流れや時期の理解が求められました。
また問6では公害問題が発生した場所についても把握しておく必要がありました。
第5問
作家田辺聖子に関する年譜をテーマに、太平洋戦争期から現代について総合的に出題されました。
問3では阪神・淡路大震災の処理にあたった内閣について出題されました。
2025年は地震発生から30年という節目の年であることから、出題を予想していた受験生もいたかもしれません。
1990年代に関する問題が出題されるのは、共通テスト本試験では初めてのことでした。
新高3生・高2生へのアドバイス
2025年から始まった、共通テスト「歴史総合、日本史探究」では、昨年までの共通テスト日本史Bと同様に、ただ人物名や出来事の名前を覚えていても対応できないような出題となっていました。
基本的な知識について「いつ・どういう背景で起きたのか」を理解しておくことが求められます。
また資料問題も頻出で、リード文や資料の内容をもとに、知識と紐づけて考える力が求められます。
日頃の学習でも、一問一答の学習にとどまらず、教科書を精読して理解を深めながら、演習を通して思考力・考察力を身につけましょう
また歴史総合では、日本史の知識だけでは対応できない問題も出題されました。
日本史探究のみではなく、歴史総合の世界史分野についても丁寧に学習を進めましょう。
日本史の共通テスト対策