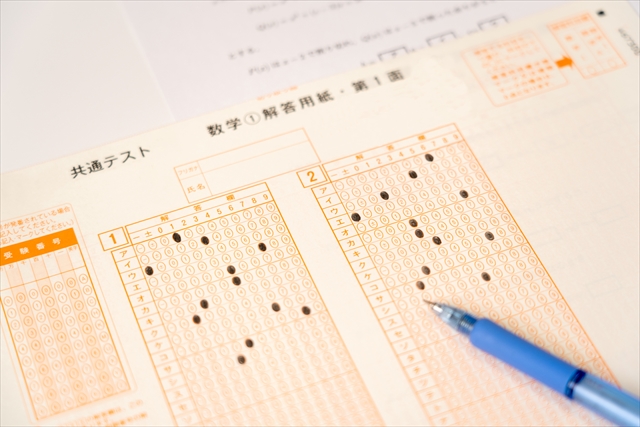このページでは、令和6年度(2024)の大学入学共通テスト公民の「倫理,政治・経済(倫理・政経)」「倫理」「政治・経済」の出題について解説します。
目次
新課程
新「公共、倫理」
【公共分野】
今年度からの新しい科目なので、出題がどうなるか不安な受験生も多かったと思われますが、総じて基本的な知識・内容があれば解答できる問題でした。
旧「政治・経済」などで出題された要素・用語を、よりかみ砕いて平易にして問われているパターンも散見されます。
思想分野もどこまで問われるか動向が読みづらかったですが、旧「現代社会」で問われるような代表的な思想家が公共でも問われていました。
難易度は平易だといえるでしょう。
【倫理分野】
第3問が源流思想と西洋思想、第4問が日本思想、第5問が認知に関する心理学、第6問が現代社会の諸課題で、第3問から第6問が倫理分野からの出題という点は、2022年に公表された試作問題から変更はありませんでした。
標準的な知識から踏み込んだ理解が必要な問題もあり、正確な読解力や論理的な思考力が求められる問題も多く見られました。
第5問は、新課程で大きく取り上げられることになった認知に関する心理学からの出願であり、試作問題で見られた連動型の問題も出題されました。

第1問【公共分野】
近年議論されることの多い、男女共同参画社会についての出題でした。
問2や問3は表の読解が求められていますが、理解に時間がかかる項目などは見受けられずシンプルなタイプで、正確に読み取れば正解は導けたと思われます。
問4のリード文にあるクオータ制は、旧「政治・経済」などでも問われていました。
第2問【公共分野】
生徒が「現実社会の諸課題の解決に向けて、人と人とが対話や議論をする公共空間を持続的に形成するには、どのようなことを考えるべきか」という議題について話した探究活動をテーマに、思想への理解や図表を読み取る力が問われています。
問1の肢にあるアーレントやハーバーマスはいずれも押さえておきたい思想家。
問2は表が2種類あり読解が大変です。
一応、「読取りに関する部分には下線を付している」とはありますが、結局肢のほとんどに下線が引かれているので、リード文をもとに正確に読み取るほかありません。
問3のような帰納⇔演繹の概念も頻出なので押さえておきたいです。
第3問【倫理分野】
現代の日本文化を反映してだと思いますが、「推し」を導入として、主に芸術をテーマにして、源流思想から西洋思想まで幅広く出題されました。
標準的な知識が必要となる問題もありましたが、問2ではモスクの装飾について、問5では『維摩経』の内容や玄奘について、踏み込んだ知識が求められていて、難易度が高いと言える問題もありました。
問9では、場面1から3の内容を読み取ると同時に知識も求められていて、また判断に迷う選択肢もあったため、時間を必要としたかもしれません。
第4問【倫理分野】
日本の思想をテーマにして、古代から現代までの幅広い時代の内容が出題されました。
標準的な知識が求められた問題が多かったですが、問5については、レポート中の「雑居」という用語から、加藤周一か丸山真男かを区別するのは難しいと感じた受験生は多いかもしれません。
第5問【倫理分野】
記憶やバイアスをテーマにした出題でした。
問3のように、ソクラテスやJ.S.ミルといった哲学者の知識が必要な問題もありましたが、全体的に知識よりも読解力や論理的な思考力が求められる問題が多く、聞き慣れない用語が登場したり、問題文を丁寧に読み進める必要があったりして、戸惑ったかもしれません。
問3では、各哲学者の思想への理解と、会話文に出てくる「クリティカル・シンキング」への理解が必要でした。
問5は、緊急時の行動と認知バイアスをテーマにした連動型の問題でした。
新傾向の問題だったのと、思考力が求められる問題で困惑したかもしれません。
第6問【倫理分野】
戦争と平和をテーマにした出題でした。
問1から問3では、必要とされる知識は標準的でした。
問4では会話文、問5では比較的文章量の多い資料文の読解力が求められましたが、丁寧に読み進めていくことができれば解答できたと思います。
新「公共、政治・経済」
公共分野は基本知識さえ押さえていれば比較的正解が導きやすいものが多かったのに対し、
政治・経済分野は参照しなければならない表の数や条文の文章量なども相当に多く、ある意味集中力も求められる構成になりました。
一部抽象的な語句や概念も散見され、骨があると感じた受験生も一定数いたと思われます。
公共分野と総合すれば、難易度は標準的ではありましたが、今後も思考型の問題や資料の読み取り問題に対応する力はつけていく必要があるでしょう。

第1問【公共分野】
近年議論されることの多い、男女共同参画社会についての出題でした。
問2や問3は表の読解が求められていますが、理解に時間がかかる項目などは見受けられずシンプルなタイプで、正確に読み取れば正解は導けたと思われます。
問4のリード文にあるクオータ制は、旧「政治・経済」などでも問われていました。
第2問【公共分野】
生徒が「現実社会の諸課題の解決に向けて、人と人とが対話や議論をする公共空間を持続的に形成するには、どのようなことを考えるべきか」という議題について話した探究活動をテーマに、思想への理解や図表を読み取る力が問われています。
問1の肢にあるアーレントやハーバーマスはいずれも押さえておきたい思想家。
問2は表が2種類あり読解が大変です。
一応、「読取りに関する部分には下線を付している」とはありますが、結局肢のほとんどに下線が引かれているので、リード文をもとに正確に読み取るほかありません。
問3のような帰納⇔演繹の概念も頻出なので押さえておきたいです。
第3問【政治・経済分野】
自身の将来や地域社会の課題について考える生徒のケースを切り口に、政治・経済分野が横断的に問われています。
問2の合区選挙は時事的なテーマとしても頻出。
都市部の受験生にはなじみが薄いかもしれないですが知っておきたいです。
問4は近年散見される思考型の問題。
「思想の自由市場」という言葉を知らなかった受験生には、抽象度が高く感じ、とっつきにくいと思われたかもしれません。
問6は国家賠償と損失補償というややマイナーな言葉が肢に含まれており、悩んだ受験生もいそうです。
第4問【政治・経済分野】
国際政治・国際経済に関する出題でした。
全体的にリード文が長く、読解に時間がかかりそうです。
キーワードは○で囲む、キーセンテンスは線を引くなど、読解の上でも頭の中を整理する工夫をしたいところです。
問1はマネーストック・マネタリーベース・国債の市場評価額といった、受験生が苦戦しがちな経済の概念が問われています。
問6は「アラブの春」に関する世論調査の問題。
ここでは直接的に問われていませんが、国際紛争についての設問は地図と併せて問われることもありますので、教科書や資料集で確認しておきましょう。
第5問【政治・経済分野】
労働政策に関しての出題でした。
問2の出入国管理法改正や「特定技能」の在留資格などは、時事的な要素が反映されています。
問4は契約自由の原則が労働契約で当てはまらない理由が問われています。
問題文の言葉が複雑で、そもそも問題文を読み解くのに苦労した受験生も多そうですが、明らかに不適と分かる肢も多く、問題文を読解できれば、正解は導けたと思われます。
第6問【政治・経済分野】
企業・市場メカニズム・検察審査会など、経済分野を中心としつつも、一部政治分野からの出題も見られた大問でした。
問1は今年度の旧「政治・経済」でも出題されていた、株式会社についての出題の焼き直しになっています。
株主代表訴訟やメインバンク制度など、難易度の高い語句が肢に含まれており、こちらのほうが解くのに苦慮しそうです。
問2も今年度の旧「政治・経済」が焼き直された、こちらは垂直な供給曲線の問題で、計算も要求されているので、戸惑った受験生も多かったのではないでしょうか。
問4・問5も基本知識を押さえたうえで資料を読み取る必要があり、時間がかかりそうです。
旧課程
旧「倫理、政治・経済(倫理・政経)」
【倫理分野】
倫理分野については、大問数4、解答数16で昨年から変更はありませんでした。
また、第1問は源流思想、第2問は日本思想、第3問は西洋思想、第4問は現代社会・青年期で、各大問の出題分野についても昨年と同様でした。
標準的な知識にプラスして細かい知識が必要なときもあり、どの大問においても正確な読解力が求められる問題がありましたが、平年並みの難易度と言えるでしょう。
【政治・経済分野】
近年みられる長いリード文を読み取らせる問題や、資料・グラフの正確な読解を試す問題が今年も見受けられました。
一部受験生にはなじみの薄い概念も出題されましたが、おおむね教科書に登場する基本知識があれば処理できる範囲のものが多かった印象です。
なお、昨年度と同様に、全設問が単独科目「倫理」「政治・経済」との共通問題でした。

第1問【倫理分野】
源流思想の分野からは、キリスト教、イスラーム、仏教、古代中国の思想、エピクロスなどについて出題されました。
標準的な知識や読解力があれば解答できる問題が多かったですが、問3のように、原罪思想についてのやや細かい知識が求められる問題もありました。
倫理においては、問1のように適当なものを全て選ぶ問題、問3のように各事柄についてそれぞれ正誤を問われる問題など、消去法では答えられない問題もあります。
第2問【倫理分野】
日本思想の分野からは、古代日本の思想、平安時代から鎌倉時代の仏教、江戸時代の思想、民俗学をはじめとした近代の思想について出題されました。
知識問題については標準的な問題が多かったです。
問3については安藤昌益に関しての知識と、正確な読解力が求められる問題でした。
第3問【倫理分野】
西洋思想の分野からは、宗教改革、レーニン、ドゥルーズとガタリ、ハーバーマスなどについて出題されました。
問1では、宗教改革に関しての細かい知識が求められました。
問2では、ドゥルーズとガタリ、レーニンの思想について理解しておく必要がありました。
問3では、2つの資料文を読んで、適切な具体例を選択する思考力が必要とされる問題でした。
第4問【倫理分野】
現代社会・青年期の分野からは、地域社会をテーマにして、プラグマティズム、神谷恵美子、マズロー、アドラーなど幅広い内容が出題されました。
問3では、アドラーの思想を理解している必要がありました。
問4は、リード文と会話文の両方を踏まえて、適当なものを選択する問題でしたが、正確な読解力と論理的な思考力が求められました。
第5問【政治・経済分野】
市場メカニズム・GDP・国際経済など、経済分野からの出題でした。
問1のように垂直/水平な需要曲線は、大学受験の範囲ではあまりなじみがなかったかもしれません。
問3は通貨体制の変遷についての問題。
肢が多いですが、それぞれの体制を押さえていたら解答はできるはずです。
問5は近年頻出のジニ係数が絡んでいます。
このように、リード文にも特に説明なく当たり前に使われているので、しっかり概念を押さえておきましょう。
第6問【政治・経済分野】
法体系について、政治分野からの出題でした。
リード文が長い問題も多く、法学が「文字で学ぶ学問」であるということを窺わせます。
問4の違憲法令審査権に関する知識は頻出なので、必ず押さえておきたいところです。
第7問【政治・経済分野】
「公正な地球社会の実現」というテーマのもと、政治・経済分野が横断的に問われています。
探求がテーマになってはいますが、リード文を正確に読解し、教科書に登場するような語句を押さえておけば、正解にはたどりつけるでしょう。
旧「倫理」
大問数4、解答数33で昨年から変更はありませんでした。
また、第1問は源流思想、第2問は日本思想、第3問は西洋思想、第4問は現代社会・青年期で、各大問の出題分野についても昨年と同様でした。
標準的な知識にプラスして細かい知識が必要なときもあり、どの大問においても正確な読解力が求められる問題がありましたが、平年並みの難易度と言えるでしょう。

第1問
源流思想の分野からは、キリスト教、イスラーム、仏教、古代中国の思想、エピクロスなどについて出題されました。
標準的な知識や読解力があれば解答できる問題が多かったですが、問3のように、原罪思想についてのやや細かい知識が求められる問題もありました。
倫理においては、問1のように適当なものを全て選ぶ問題、問3のように各事柄についてそれぞれ正誤を問われる問題など、消去法では答えられない問題もあります。
第2問
日本思想の分野からは、古代日本の思想、平安時代から鎌倉時代の仏教、江戸時代の思想、民俗学をはじめとした近代の思想について出題されました。
知識問題については標準的な問題が多かったですが、問6は、設問の中で示されている『養生訓』から、思想家の名前は貝原益軒であると判断できるように学習をしておく必要がありました。
資料文の内容と一致するものを選択する問題もあり、特に問3については安藤昌益に関しての知識と、正確な読解力が求められる問題でした。
第3問
西洋思想の分野からは、宗教改革、アダム・スミス、ヘーゲル、社会民主主義、レーニン、ドゥルーズとガタリ、ハーバーマス、ポパーなどについて出題されました。
問1では、宗教改革に関しての細かい知識が求められました。
問2では、ドゥルーズとガタリやレーニンの思想について理解しておく必要がありました。
問6で登場したポパーは出題頻度が高い人物ではないため、難しさを感じたかもしれません。
第3問においても、問3や問4のように、ある人物に関する知識と資料文の内容を正確に読み取る力が求められる問題が出題され、問7では、2つの資料文を読んで、適切な具体例を選択する思考力が必要とされる問題でした。
第4問
現代社会・青年期の分野からは、地域社会をテーマにして、スチュワードシップ、プラグマティズム、神谷恵美子、マズロー、アドラー、レヴィン、ヒューマニズム、ノーマライゼーションなど幅広い内容が出題されました。
問1では、2021年の共通テスト第2日程の問題文中に登場したスチュワードシップの内容についての問題でしたが、学習ができていなかった受験生はいるかもしれません。
問3では、アドラーの思想を理解している必要がありました。
問5では、見知らぬ人との交流に関して行われた実験に関する資料と図をもとに、適当な考察を選択する思考力が求められました。
旧「政治・経済」
近年みられる長いリード文を読み取らせる問題や、資料・グラフの正確な読解を試す問題が今年も見受けられました。
一部受験生にはなじみの薄い概念も出題されましたが、おおむね教科書に登場する基本知識があれば処理できる範囲のものが多かった印象です。
特に経済分野において、受験生が苦戦しがちな抽象的な概念が問われています。
難易度はやや易化もしくは例年並みと言えます。

第1問
「国民の意思」に基づく政策決定をテーマに、政治・経済分野が横断的に出題されています。
問2は旧現代社会の第1問-問5を焼き直した問題ともいえます。
近年ニュースなどで目にすることも多い電力事業の自由化を題材に、外部不経済・規模の経済など、抽象的で受験生が理解しづらい言葉が問われました。
問3は無担保コールレート(翌日物)とマネタリーベースの推移から問われています。
日本銀行の金融政策も理解しづらいと感じる受験生は多いですが、用語の丸暗記ではなく、しっかり日銀と金融市場の関係を図起こしして理解しましょう。
問5のクオータ制などの言葉も頻出です。
第2問
市場メカニズム・GDP・国際経済など、経済分野からの出題でした。
問1のように垂直/水平な需要曲線は、大学受験の範囲ではあまりなじみがなかったかもしれません。
問5は通貨体制の変遷についての問題。
肢が多いですが、それぞれの体制を押さえていたら解答はできるはずです。
問7は近年頻出のジニ係数が絡んでいます。
このように、リード文にも特に説明なく当たり前に使われているので、しっかり概念を押さえておきましょう。
第3問
法体系について、政治分野からの出題でした。
リード文が長い問題も多く、法学が「文字で学ぶ学問」であるということを窺わせます。
問5の違憲法令審査権に関する知識は頻出なので、必ず押さえておきたいところです。
問8の難民条約に関する問題も、与えられた法律の条文をきちんとかみ砕いて理解できるかという読解力が問われています。
第4問
「公正な地球社会の実現」というテーマのもと、政治・経済分野が横断的に問われています。
探求がテーマになってはいますが、リード文を正確に読解し、教科書に登場するような語句を押さえておけば、正解にはたどりつけるでしょう。
新高3生・高2生へのアドバイス
新「公共、倫理」
【公共分野】
今年度からの新科目なので、対策が不安な生徒も多いと思いますが、必要知識はかつての公民とさほど変化はありません。
しっかり基本的な用語を押さえることと、特に経済分野において複雑な単元(需要・供給曲線、日銀の金融政策、円高・円安などの概念)は、しっかり自分で繰り返し図起こしをして理解しましょう。
時事的な出来事に対する知識も問われています。
学校の図書館やスマートフォンのアプリなどで新聞を読む習慣をつけるとよいでしょう。
新聞各社の社説欄にひとまず目を通してみて、大まかに1日のニュースの概要を知り、自分なりの意見をつくってみるのもおすすめです。
【倫理分野】
倫理では、知識が求められる問題、資料文を読み取る問題、論理的な思考力が必要な問題に分けられます。
学習する上で、「プラトン」と「イデア」のように、まず人物名と用語がリンクさせられるようにしてみましょう。
また、思想家に関連する著作名も一緒におさえておくようにしてみてください。
高得点を狙う場合は、出題頻度が少ない人物や用語も覚えていくようにしたいところです。
次にその人物の思想や用語の内容を理解していくようにしましょう。その際に、具体的な例も意識しながら学習を進めていけるとベストです。
読解力や思考力が求められる問題は、模試、過去問、問題集を活用して練習を重ねていきたいところです。
文章量が多いと困惑してしまうときもあるかもしれませんが、丁寧に読み進めていけば解ける問題も多いので、落ち着いて問題に取り組んでみてください。
新「公共、政治・経済」
実際の共通テストでは確かに、思考力を問われる問題、抽象→具体といった思考の転換が求められる問題、多く複雑な図表を読み取る問題などが出題されますが、そのベースにあるのは基本的な用語を多く理解していくという地道な勉強です。
とにかく受験学年の夏ごろまでには、教科書に登場するような基本的な用語は習得しきることを目指しましょう。
ただ、経済の一部分野(需要・供給曲線、日銀の金融政策、円高・円安などの概念)は丸暗記で対応しきれないものも多いです。
しっかり自分の手で何度も図起こしをして、体にしみこませましょう。
秋頃は模試や演習を通して、実際の問題で覚えた用語などをどう生かすかのテクニックを身につけていきたいところです。
また、リード文に適合する政策を選ばせるなど、思考力を試す問題も多いです。
学校の図書館やスマートフォンのアプリなどで新聞を読む習慣をつけるとよいでしょう。
新聞各社の社説欄にひとまず目を通してみて、大まかに1日のニュースの概要を知り、自分なりの意見をつくってみるのもおすすめです。
新聞にはグラフや表も多用されるので、図表を読み取る問題に対応する練習にもなります。
旧「倫理、政治・経済(倫理・政経)」
【倫理分野】
倫理では、知識が求められる問題、資料文を読み取る問題、論理的な思考力が必要な問題に分けられます。
学習する上で、「プラトン」と「イデア」のように、まず人物名と用語がリンクさせられるようにしてみましょう。
また、思想家に関連する著作名も一緒におさえておくようにしてみてください。
高得点を狙う場合は、出題頻度が少ない人物や用語も覚えていくようにしたいところです。
次にその人物の思想や用語の内容を理解していくようにしましょう。その際に、具体的な例も意識しながら学習を進めていけるとベストです。
読解力や思考力が求められる問題は、模試、過去問、問題集を活用して練習を重ねていきたいところです。
文章量が多いと困惑してしまうときもあるかもしれませんが、丁寧に読み進めていけば解ける問題も多いので、落ち着いて問題に取り組んでみてください。
【政治・経済分野】
全体的に、長いリード文を正確に読解する力、資料やグラフを読み取る能力が試されています。
政治分野においては、国内/国際政治ともに、憲法や重要法律の条文をきちんと理解する力や、基本語句のみならず時事的な出来事に対する知識も求められます。
学校の図書館やスマートフォンのアプリなどで新聞を読む習慣をつけるとよいでしょう。
新聞各社の社説欄にひとまず目を通してみて、大まかに1日のニュースの概要を知り、自分なりの意見をつくってみるのもおすすめです。
経済分野は、抽象的な言葉をケースとともに理解することや、需要・供給曲線やジニ係数/ローレンツ曲線などグラフが登場する分野は、自分の手で実際にグラフを書いてみて図起こしして考える癖をつけましょう。
旧「倫理」
倫理では、知識が求められる問題、資料文を読み取る問題、論理的な思考力が必要な問題に分けられます。
学習する上で、「プラトン」と「イデア」のように、まず人物名と用語がリンクさせられるようにしてみましょう。
また、思想家に関連する著作名も一緒におさえておくようにしてみてください。
高得点を狙う場合は、出題頻度が少ない人物や用語も覚えていくようにしたいところです。
次にその人物の思想や用語の内容を理解していくようにしましょう。その際に、具体的な例も意識しながら学習を進めていけるとベストです。
読解力や思考力が求められる問題は、模試、過去問、問題集を活用して練習を重ねていきたいところです。
文章量が多いと困惑してしまうときもあるかもしれませんが、丁寧に読み進めていけば解ける問題も多いので、落ち着いて問題に取り組んでみてください。
旧「政治・経済」
全体的に、長いリード文を正確に読解する力、資料やグラフを読み取る能力が試されています。
政治分野においては、国内/国際政治ともに、憲法や重要法律の条文をきちんと理解する力や、基本語句のみならず時事的な出来事に対する知識も求められます。
学校の図書館やスマートフォンのアプリなどで新聞を読む習慣をつけるとよいでしょう。
新聞各社の社説欄にひとまず目を通してみて、大まかに1日のニュースの概要を知り、自分なりの意見をつくってみるのもおすすめです。
経済分野は、抽象的な言葉をケースとともに理解することや、需要・供給曲線やジニ係数/ローレンツ曲線などグラフが登場する分野は、自分の手で実際にグラフを書いてみて図起こしして考える癖をつけましょう。
公共・公民の共通テスト対策