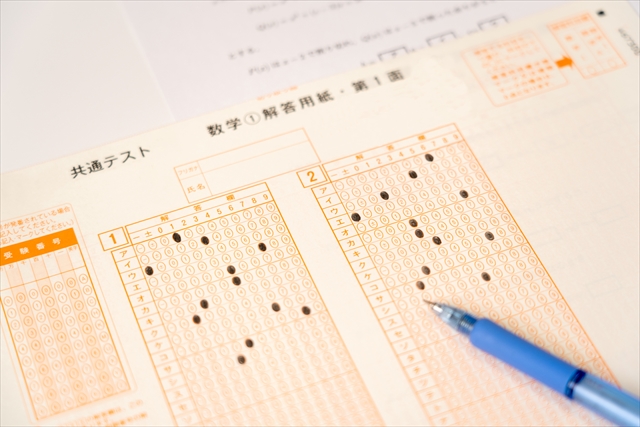このページでは、令和7年度(2025年度)の大学入学共通テスト理科の「化学」の出題について解説します。
化学
2025年度入試においても、共通テストになってからの特徴である“思考力が問われる”設問が随所に散りばめられ、歯ごたえのある問題構成でした。
全体としては分量がやや多く、全問題を解答するには時間が足りない受験生が多かったでしょう。
共通テスト化学では、計算が絡む問題ほど正答率が下がる傾向がありますが、それは“ただ公式を当てはめるだけの計算ではない”ことが一因といえます。
・図表やグラフから必要な数値を読み取る必要がある計算
・与えられた複数の情報がどう繋がるかを考えて、立式する必要がある計算
などのように、解答に至るまでに複数のstepを踏まなければいけない問題が多く、一見すると何をしてよいかわからない受験生が多いのです。
ここで大切なのは、“基礎の計算を正しく理解すること”と“与えられた情報の整理”です。
特に、与えられた情報を自分なりの言葉で整理できたかどうかが2025年度入試においても大きく明暗を分けたでしょう。

以下、大問ごとに注目すべき問題についてコメントしていきます。
第1問 物質の状態
問3
気体の溶解度に関して、用いる知識は「水に溶解する気体の物質量は、水の体積と気体の分圧に比例する」という1点だけです。
本問のように、変化の前後を考えさせる問は頻出ですが、前後の物質量や圧力の関係を自分で書きながら整理すれば、「変化前に溶解していた二酸化炭素の物質量」が、「変化後に溶解している二酸化炭素の物質量」と「容器外に逃げた二酸化炭素の物質量」の和であることに気づき、立式ができたでしょう。
問4
コロイドに関して誤りの選択肢を選ぶ正誤問題でした。
誤りの選択肢だけ知識の難易度が高かったですが、他4つの選択肢は基本知識で確実に正しいと判断できますので、消去法で正解にたどりつくことができます。
問5
aは沸騰について正しく理解していれば、難なく正答できます。
bは逆浸透をテーマにした、やや難の問題でした。
浸透圧では、力の向きを図示して考える習慣をつけましょう。
そうすると、溶液側にかかる浸透圧が、与えられた2つの数値の引き算であることに気づき、ファントホッフの法則から、浸透後の溶液のモル濃度を求められます。
第2問 物質の変化
問2や問4a・cは、いずれも基本問題なので、確実に得点したい問題です。
問3
何をしたらよいかわからないと戸惑った受験生は多く、正答率は低いでしょう。
このようなときこそ“基礎にもどって考える”ことです。
まず、電離平衡における基本として、 Ka=ca2と[H+]=caの2式から、aを消去して[H+]を水溶液のモル濃度c で表してみます。
次に、“具体的な値で考えてみる”ことです。
たとえば、水溶液の体積が10倍になるとき、すなわちモル濃度cが1/10になるときを考えてみると、式から
問4 b
平衡に達したときの物質量の量的関係を整理してみれば、アンモニアのモル分率がわかり、すると図1から温度を求められることに気づいたはずです。
本問は「平衡後のアンモニアのモル分率を求めよ」という問題と、計算過程は同じですが、直接的にこれが書かれていないため戸惑った人もいるかもしれません。
問3もそうでしたが、まずは、『わからなくても手を動かして基本計算をしてみる』ことがヒントになります。
第3問 無機化学
計算問題は、例年に比べると複雑さはなく解きやすい問題でした。
知識問題も基本知識をしっかり習得できているかが問われています。
問1の選択肢②は、誤りかどうかを判断できない受験生は多かったと思いますが、残りの①③④を基本知識で正しいと判断できるので、消去法で②が誤りだと選ぶことができます。
無機化学の学習では、酸化還元反応が関係するものが多いので、ふだんの学習からも意識するようにしましょう。
第4問 有機化学・高分子化合物
例年どおり、全体として、教科書で学ぶ基本知識が正しく整理できているかが問われました。
問2では、Ⅲ「分子量が179.0」という条件をどう使えばよいのか悩んだ受験生も多いかもしれませんが、「86.0+93.0=179.0」という関係から、分子量が変化する縮合反応ではなく、分子量が変化しない付加反応であることに気づけたかがポイントです。
問4cは高分子の分野で苦手な人が多い、ビニロンの計算を応用したものでした。
まずは基本計算をしっかり使いこなせるように定着させていきましょう。
第5問 総合問題
総合問題ではありますが、それぞれの小問ごとに独立しているので、できる問題から解答していくことが大切です。
問1がやや難の知識でしたが、問2、問3a・bは各分野の基本知識で解答できる問題でした。
問3cもそれぞれの経路について、「反応エンタルピー=生成エンタルピーの総和の差」という基本公式を活用すれば、難なく計算できます。
問3dも、見慣れない反応ですが、与えられた情報を整理し、体積の変化などに注意して計算すれば正答にたどり着くことができます。
化学では、このように実験を追っていく問題が多いですから、その流れを簡単な図解で書き出して整理する癖をつけましょう。
化学の共通テスト対策