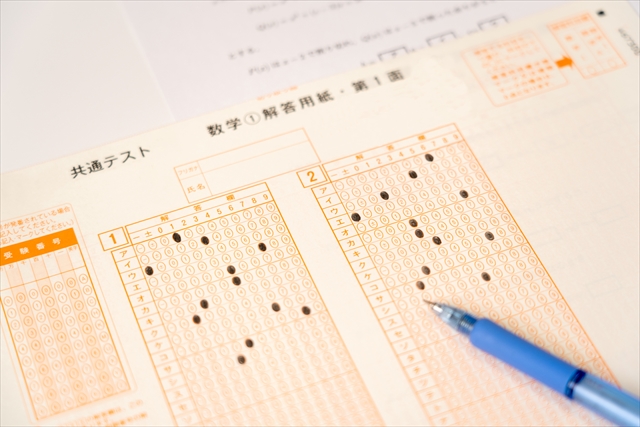このページでは、令和7年度(2025年度)の大学入学共通テスト公民の「現代社会」の出題について解説します。
現代社会
複雑な資料や表を読み取ったうえで解答を求められる問題が増加しています。
多数の資料を目にすると、それだけで面食らってしまう気持ちもわかりますが、落ちついて、今まで学習してきた内容と登場している資料の何が結びついているかを見ていきましょう。
全体的な難易度はやや易化もしくは例年並みと言えます。

第1問
労働や社会保障をテーマにした出題でした。
問4など文章量が若干多い設問も散見されますが、正確に文脈を追えばそれほど苦労はしないはずです。
問5は抽象的で、受験生が理解しづらい外部不経済・情報の非対称性・非価格競争などの用語が問われています。
このリード文のように、特に経済用語はしっかり例とともに押さえましょう。
問6も「取組み」から具体的な例を選ばせる問題です。
このように抽象→具体と問題が展開する例は今後も増加すると考えられるので、しっかり演習を通して慣れていきましょう。
第2問
地方自治・選挙制度をテーマにした出題でした。
問1の、「地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できる」ことは頻出です。
問4は労働市場における需要・供給曲線が出題されています。
傾向としては、縦軸に財・サービスの価格がとられるものが多いので、やや戸惑ったかもしれません。
問5も資料の設定に従って正確に計算する必要があります。
第3問
日本国憲法や司法をテーマにした出題でした。
今までの大問に比べて、知識があれば処理できる問題も多い印象です。
問5の肢に含まれるグラミン銀行、アジアインフラ投資銀行などの語句は、現代社会としてはやや細かいです。
問7は思想の問題です。
過去マイナーな思想家が問われることもありましたが、今回肢に出ているのはロールズ・ミル・ベンサムと、教科書にもよく出てきやすい思想家でした。
第4問
国際政治をテーマにした出題でした。
問2の肢にある信託統治理事会について、活動休止になったという知識は問われやすいので注意です。
問3の国連分担金の各国比率も押さえておきましょう。
問4・問5は第4問にも登場した思想の問題ですが、こちらも標準的な内容です。
問7は近年よく取り上げられるゲーム理論が絡んだ出題でした。
第5問
医療に関する地域課題を例に、表やグラフを読み取る力が要求される問題でした。
問3もリード文が長いですが、文脈にそって正確に読み取れば正解できるはずです。
問4のリード文にもあるように、医療サービスの不足は、都市部に含めて各地に今も存在する問題です。
今後もこのテーマの出題がある可能性もあるので、新聞記事などから自分の意見をまとめておいてもよいでしょう。
新高3生・高2生へのアドバイス
総評に記したとおり、複雑な資料や表を読み取ったうえで解答を求められる問題が増加しています。
初見の資料であったとしても、「今まで学習した内容と何か結びつかないだろうか?」と糸口を探すことが大切です。
まずは教科書や授業を通してしっかり知識を粘り強く習得していきましょう。
また、近年は抽象度が高い用語の意味を理解しているかどうかを問う問題も増えています。
特に経済分野においては抽象度が高い用語も多いので、しっかりケースとともに理解したいところです。
さらに、第5問の問4のように、リード文に合致する政策を選ばせる問題は新課程においても同様にみられると思われるので、新聞記事やニュースなどから、しっかり自分の意見をまとめておく習慣をつけておくことも大切でしょう。
現代社会の共通テスト対策