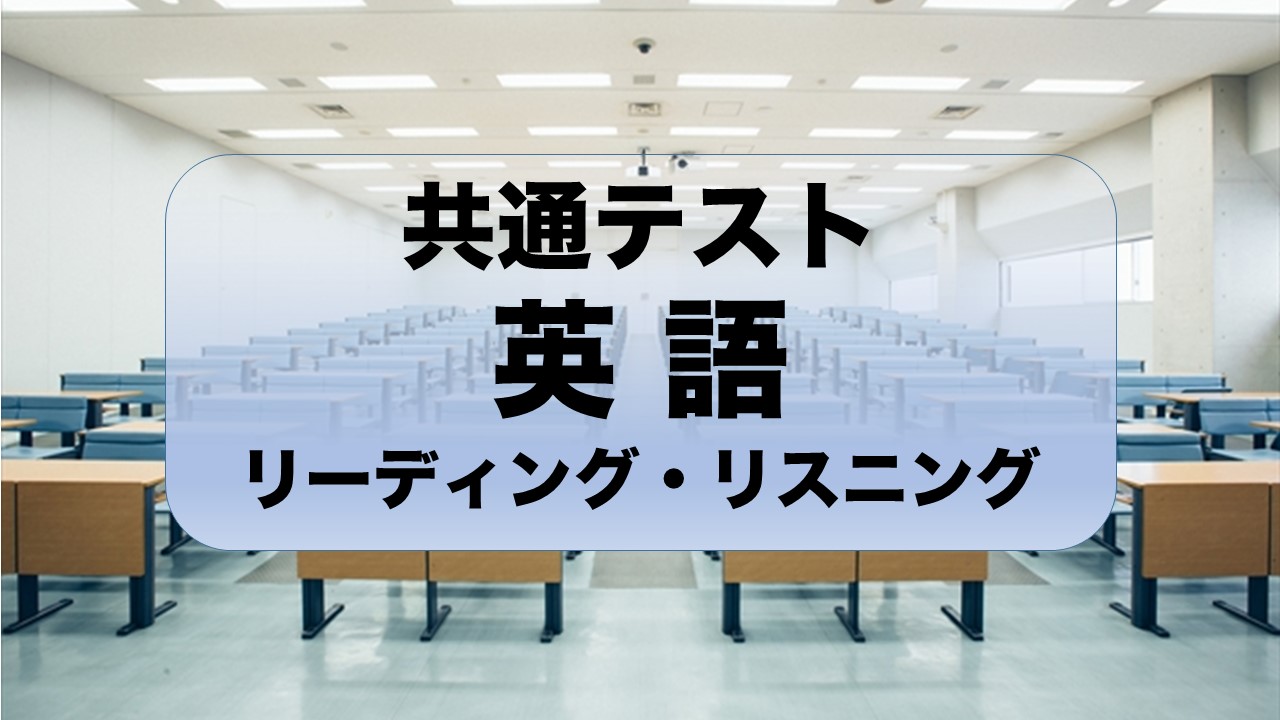このページでは、令和7年度(2024年度)の大学入学共通テストの「英語(リーディング・リスニング)」の出題について解説します。
目次
英語(リーディング)
今年度から大問構成に変更があり、従来の6問から8問へと変更になりました。
解答数は昨年度の49から5つ減って44となり、英文の分量もリード文や設問・選択肢まで合わせた総語数は、昨年度の約6,300語から約5,600語へと700語程度減少しました。
大問の内容に関して、従来なかった新形式の問題が2題含まれていましたが、いずれも大学入試センターから事前に試作問題として公表されていた内容と同様の形式でした。
各英文のトピックに大きな変化はなく、一般的な論説文からパンフレットやブログ記事、物語、メールの文面などが出題され、レベルも標準的で概ね読みやすい内容でした。
また、従来同様に複数箇所の情報を参照しなければならない設問や、本文に述べられていない内容を推測する設問が出題されていましたが、全体的に正答に該当する情報は読み取りやすく、選択肢も素直な作りのものが大半で判別に迷うようなところはありませんでした。
そのためテスト全体の難易度は、これまでより易しい内容であったと言えます。

第1問
初めて自宅で魚を飼おうとしている人に向けて、水槽の環境作りに関するアドバイスを掲載したパンフレットでした。
問3は、本文で提示されたアドバイスと一致する水槽として正しいものをイラストで選ぶ問題でしたが、本文で提示されている情報とイラストを丁寧に落ち着いて確認しないと判断に迷う可能性がありました。
第2問
「空を飛ぶ乗り物」に関する公開討論会に参加したゲストスピーカー3名の意見を紹介するブログ記事でした。
本文で展開される各スピーカーの意見は明快で読みやすいものでした。
また、この大問では例年共通テストで見られる「事実と意見を区別する」設問として、一人のスピーカーの「意見」を選択する設問が出題されましたが、これも特に迷うところはありませんでした。
第3問
従来のテストで第3問Bとして出題されていた形式で、今回はコンテストに応募したバンドの成長を描いた物語が素材でした。
場面設定がイギリスであるため、本文内にはイギリス英語のつづりや表現が見られました。
設問では人物関係や時系列の整理を求められるものが含まれていましたが、本文は素直な展開でしたので情報の整理に苦戦することはなかったと思われます。
ただし、時系列整理の問題で使用しなかった選択肢については、本文を丁寧に読んでいないと解答に必要なものに見えるという点で注意が必要でした。
第4問
事前に公表されていた試作問題の1つで、「スローライフの実践」に関して生徒が書いたエッセーに、教師が添削を加えた原稿を題材とした問題です。
英語の論理展開を理解し、それに沿った英文を作成する力が身についているかどうかを確認する設問が並びました。
順接や逆接、譲歩、言い換えといった論理関係の理解はどの言語を駆使するにも必要な要素ですので、英語や日本語に関係なく、普段からこれらの論理関係を意識した学習を心がけましょう。
第5問
「地元のビジネスに関する会議」の準備を担当するボランティアの大学生と、会議の責任者である教授との間のメールのやり取りを用いた問題でした。
このように複数の情報源が提示される問題では、基本的にそれらの情報を組み合わせて正解を判断する設問が含まれます。
今回も、問2は生徒のメールに含まれるスケジュール表と教授がメールで提示した情報を丁寧に突き合わせないと、2つの空欄を正しく埋めることができないようになっていました。
また、問4では教授のメールの内容から、参加者の正しい位置関係を示したイラストを選ぶことが求められました。
共通テストではリーディング・リスニングを問わず、イラストを用いた設問がいくつも出てきます。
その中で位置関係が問われた場合、場所に関する様々な表現に慣れていないとスムーズに理解することができません。
よって、人や物の位置関係を伝える英文を目にした際には、描写されている状況を具体的にイメージする習慣を付けましょう。
第6問
プロの作家を志望する友人が書いた「超能力を持つ架空のヒーローたちの物語」と、それに対する意見や感想を述べたメール本文を題材とした問題でした。
物語の主人公がどのような立場の人物であるのかが分かりづらく、またこのタイプの文章によくある「時系列の入り組んだ構成」になっていたため、「きっちり読めている」という感覚が持ちにくく、本文の読み取りに苦戦したかもしれません。
設問は時系列を整理する設問や、複数の情報から組み合わせとして正しいものを選ぶ設問など、例年と同じような構成でしたが、問3は助動詞に関する正確な知識を持っていないと正解を判断できないような作りになっており、改めて文法学習の重要性を意識させるものでした。
第7問
「動物の睡眠パターン」に関するオーソドックスな論説文と、その内容を要約したプレゼン用の資料を用いた問題でした。
文章の論理展開は素直で、一部の見慣れない単語も前後関係から意味を理解できるように配慮がされており、読みやすい文章だったと言えます。
個々の設問では、資料に含めるべきではない情報の特定や、動物の睡眠パターンを正しく示した図を選ぶものなど、共通テストらしいものでしたが、いずれも特に判断に迷う部分はありませんでした。
第8問
事前に公表されていた試作問題のもう1つで、内容は「宇宙開発の是非」に関する複数人の意見や情報源を踏まえて、テーマに対して自分の立場を決め、エッセーのアウトラインを作成するまでの一連の流れを、3つのステップに沿って追体験するものでした。
全く新しいタイプの問題ですが、各人物の主張や情報源で述べられている内容を正確に読み取り、論理的に判断すれば正解は問題なく判断できるようになっており、特殊な読み方や知識が求められているわけではありません。
英語(リスニング)
例年同様に大問数6、解答数37という構成でした。
大問の内容について、講義を聞き取って解答する第5問と複数名による会話が題材の第6問Bでは一部変更がありました。
しかし、それ以外については聞き取った内容と同じ意味の英文を選択する第1問A、正しいイラストを選択する第1問Bと第2問、2名による対話が題材の第3問・第6問A、さらに図表の穴埋めや複数の条件を満たすものを選ぶ第4問A・Bと、おなじみの問題が出題されました。
聞き取る本文の分量は約1,600語で、昨年より若干増えたもののほぼ同程度と言ってよいものでした。
読み上げ回数もこれまでと変わらず、第1問と第2問が2回、第3問以降は1回で、音声にはアメリカ英語だけでなくイギリス英語、さらに日本人と思われるノン・ネイティブの英語も含まれていました。
テストの難易度は、イギリス英語で聞き取りにくい部分があるものの、全体としては聞き取りやすく、形式の変更も解答に大きく影響するものではなかったので、昨年と同程度と考えてよいでしょう。

第1問 A
短い発話を聞いて、その内容と同じ意味を表す英文を選ぶ問題が4問出題されました。
発話自体は複雑ではなく聞き取りやすいものですが、正解は発話を端的に言い換えた内容になっています。
たとえば、問3では
Do you have any coins? This ticket machine doesn’t accept bills.
「小銭を持っている? このチケット券売機はお札が使えないんだ」
という発話が、正解では
The machine takes coins but not bills.
「その券売機は小銭は利用できるが、紙幣はできない」
と表現されていました。
このように、第1問Aでは各選択肢の意味を素早く捉えたうえで、聞き取った一部の情報だけではなく、全体を踏まえて正解を判断しなければなりません。
第1問 B
「短い発話を聞いて、その内容に合う絵を選ぶ」という形式は昨年と同様でしたが、設問数は1つ増えて合計4問となりました。
問5や6、8のように、絵を用いた問題では正解に必要な情報が段階的に提示されることがよくありますので、最後まで丁寧に聞いて正解を判断しましょう。
また、問7では being pulled という、進行+受動を表す分詞が含まれていました。
この表現が表す状況を正しく理解するためには文法の知識が必要です。
リスニング、リーディングの区別なく、英文法は英語を学ぶうえで必須であると意識しましょう。
第2問
日本語で提示された対話の場面を踏まえながら音声を聞いて、適切な絵を選ぶ問題です。
形式は昨年から変わっていませんが、設問数が1つ減って3問の出題でした。
この問題も第1問Bと同じように、正解を判断する情報が少しずつ提示されるようになっていますので、いきなり正解を判断しようとするのではなく、条件に合わない絵から除外していく意識で取り組みましょう。
たとえば、問10であれば、「日光の描かれた商品」という女性の1回目の発言から①と②を除外し、「どちらでも安い方」という女性の2回目の発言から③に解答を絞り込みます。
第3問
事前に日本語で与えられた状況を踏まえながら2人の対話を聞き、正解を選ぶ問題が6問出題されました。
第3問では、対話内に登場した単語が不正解選択肢に含まれている場合が非常に多いため、全体をしっかりと聞き取れるようにしておく必要があります。
また、問15で3つの不正解選択肢に含まれている数字がすべて対話の中に出てくるといったように、類似する複数の情報から正解に必要な情報を区別する力も求められます。
なお、この問題から音声は1回しか再生されないので、本番で慌てないように、自分なりの対応方法をあらかじめ決めておくことも重要です。
第4問 A
例年、第4問Aの2問では時系列に沿うように絵を並べ替える問題や、図・グラフを見て空欄に入る適切な情報を選ぶ問題が出題されます。
今年度は並べ替え問題は出題されず、1つ目が「大学生の朝食の好み」が年度によってどう変化しているのかを把握する、2つ目が「旅行先の週間天気予報」についていくつかの曜日の天気を答えるというものでした。
1つ目の問題では、 steadily decreased「着実に減少している」 、 rose fairly consistently「一貫して上昇している」 といった表現と折れ線グラフの推移を一致させることができるかどうかがポイントでした。
2つ目の天気予報の問題は曜日ごとの切れ目が少し分かりにくく、情報量も多かったため戸惑ったかもしれません。
第4問Aでは正解につながる情報が次々と流れていくため、必要な情報を聞き取った段階で解答を特定させ、続きを聞くことができるように普段から練習しておく必要があります。
第4問 B
こちらも例年と同じく、4人の音声を別々に聞き、条件に当てはまる選択肢を選ぶ問題が1問出題されました。
今回は、「サーフィンができる海」に関して、それぞれ異なるビーチを紹介する4人の話を聞き、問題用紙に示された3つの条件すべてを満たすビーチを選ぶ問題でした。
この問題では、条件の比較が目的であることから、各話者は同じような情報を述べるため、3つの条件をしっかり把握したうえで音声を聞く必要があります。
また、条件に沿わないことが話された段階で即座に不正解と判断する姿勢も重要です。
たとえば、選択肢④では2文目で the waves are often over 2 meters high「波は2メートルを超えることが多い」 と述べられており、この情報を聞いた段階で残りの部分を聞かずとも不正解と判断することが可能です。
第5問
「講義を聞いてワークシート内の空欄を埋める」という基本的な枠組みは例年同様でしたが、新形式の設問として、一緒に学習しているほかの生徒の発言を聞き、その内容が講義の内容と一致しているかどうかを判断するというものが加えられました。
この変更については、事前に大学入試センターが公表していた試作問題と全く同じ形であったため、特に戸惑うところはありませんでした。
講義のトピックは「regift(誰かからもらったプレゼントを、別の誰かにあげること)」という贈答文化に関するものでした。
この単語自体は初めて見たとしても、内容は身近なものであることから特に聞き取りにくいといったことはなかったと思われます。
ただし第5問は本文が長いため、ある程度余裕を持って聞き取れるだけのリスニング力がないと、正解につながる情報を聞き逃したり、本文とワークシートの言い換えに気づけなかったりするため、普段からリスニング学習に十分な時間を充ててきたかどうかで差が付く問題だと言えるでしょう。
第6問 A
例年同様、長めの対話を聞いて、その内容に関する2つの問いに答える問題でした。
対話のテーマは「食事の取り方」で、それぞれの話者の発言内容を踏まえて解答する設問が1つずつ用意されていました。
「食事」という誰にとっても普遍的なテーマであるものの、内容は「食べ物を噛む回数とその効果」という頻出とはいえない事柄についてのものであったため、情報を整理しづらい部分があったかもしれません。
第6問 B
昨年度までは4名による会話を題材とした問題でしたが、今年度は話者が1人減って3名の会話に変更されたため、聞き取りの負担が軽減されたと言えます。
一方、設問の内容は昨年度までとほとんど変わらず、会話終了時点で提示された条件に当てはまる話者の人数を答えるものと、ある1人の話者の考えの根拠となる図表を選ぶものでした。
1つ目の設問では「鳥にえさを与えるべきではない」という意見を持つ話者の数が問われましたが、過年度の問題のように、今回も最後に賛成から反対に転じた話者がいましたので、話者ごとの発言内容を注意深く追う必要がありました。
2つ目の、考えの根拠となる図表を選ぶ問題では、それぞれの図表で扱われているテーマは大きく異なっているため、細かい違いを気にする必要はありません。
ですので、事前に図表の大まかな内容を確認したうえで各話者の発言と付き合わせれば、十分に解答可能です。
新高3生・高2生へのアドバイス
英語(リーディング)
今年度の共通テストは英文の語数が減少し、分量的な負担が軽減されたように見えますが、80分という解答時間で読み切るのは容易ではありません。
また、設問も本文の一か所を読めば答えられるような単純なものだけでなく、本文の情報を基に書かれていない事柄を推測するものや、複数箇所の情報を同時に正しく理解することで初めて正解にたどり着けるものがいくつもあります。
よって、共通テストで優れた結果を出すために何よりも大切なことは、文法や構文、語彙の基本的な知識に支えられた、確かな読解力を身につけることであると言えます。
そのうえで、トピックや分量、出題形式の異なる様々な文章を読むことで、共通テストの英文を時間内に読みこなし、設問を適切に処理するスピードが磨かれていくのです。
皆さんは基礎を身につけないままに何となく英文を読んだり、表面的なテクニックを追い求めたりするのではなく、本質的な英語力を伸ばすことを意識して日々の英語学習に取り組みましょう。
英語(リスニング)
ここまで確認してきたように、共通テストのリスニングは単純な対話の聞き取りにとどまらず、発話の内容を端的にまとめた英文を選択する問題や、音声の内容に一致する絵を選ぶ問題、さらには音声を聞きながら図表やワークシートを完成させる問題や、複数人の発言内容を正しく区別する問題など、実に多様な出題形式を通して実施されます。
そのため、共通テストのリスニングでは流れてくる音声をただ受動的に聞き続けるのではなく、問題ごとに適切な対応方法を理解し、能動的に音声を聞いて正解を判断していく姿勢が求められます。
このようなリスニングができるようになるために、まずは共通テストだけを意識した学習にこだわるのではなく、毎日の学習にリスニングをしっかりと取り入れ、英語そのものを聞き取る力を磨くように意識しましょう。
共通テスト固有の対策は本質的なリスニング力があって初めて可能になるものだということを理解し、日々のリスニング学習に励んでください。
英語の共通テスト対策