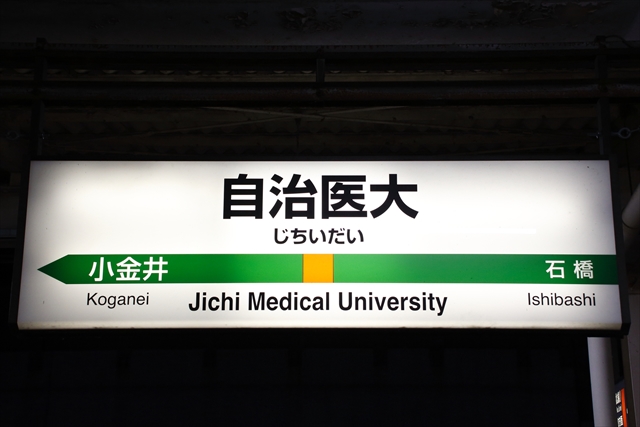こんにちは!四谷学院の奥野です。
新潟大学は、新潟県新潟市にキャンパスを持つ国立の総合大学です。大学設立の起源は1870年、新潟の共立病院設置まで遡り、約150年の歴史と伝統があります。
旧制新潟医科大学と旧制新潟高校を母体に、師範学校や長岡高等工業学校、新潟県立農林学校などが集まり、1949年5月に新制国立大学として開校しました。
総合大学としての教育資源を活かし、所属学部の専門分野をベースに副専攻として幅広い分野を学べる「NICEプログラム(全学分野横断創生プログラム)」をはじめ、特色ある取り組み・事業が展開されています。
この記事では、新潟大学の偏差値や難易度、入試の特徴や合格するための効率的な勉強方法をご紹介します。新潟大学の受験を考えている方、勉強しているのに成績が伸び悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
※本記事に記載されている情報は2024年11月27日現在のものです。最新の情報は大学公式ホームページにて必ずご確認ください。
目次 [非表示]
新潟大学の概要
新潟大学は伝統と進取の精神のもと、大学理念として「自律と創生」を掲げています。この理念に基づき、地域だけでなく世界の発展に資する知の拠点として、教育・研究・社会貢献を行っています。
そして、アドミッション・ポリシー(入学者受入れの方針)では、「求める学生像」として以下を定めています。
求める学生像
新潟大学は、自律と創生を全学の理念とし、教育と研究及び社会貢献を通じて、世界の平和と発展に寄与することを全学の目的としています。
この理念の実現と目的の達成のために、学位授与の方針に掲げるとおり、教育の基本的目標を、新潟大学の総合力を活かした学位プログラムを通じて、高い見識と良識をもって社会や時代の課題に的確に対応して、課題解決のために活躍できる人材を育成することに置いています。 以上の教育の基本的目標を実現するために、次に掲げるような資質豊かな学生を広く求めます。
- 修学に適う、確固たる学力を身に付け、新しい課題に意欲的に取り組もうとする人
- 人間性を大事にし、広い視野からものごとを考えようとする人
- 地域社会や世界の様々な場面で役に立ちたいと思っている人
新潟大学では、学部・学科ごとにディプロマ・ポリシー(学位授与の方針)、カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)およびアドミッション・ポリシー(入学者受入れの方針)が策定されています。
詳細は、大学公式ホームページの新潟大学の“三つのポリシー”よりご確認ください。
新潟大学にはキャンパスが2つあり、医歯学系の学部が旭町キャンパス、それらを除く8学部が五十嵐キャンパスを使用します。
大学名:新潟大学
設立年:1949年
学生数:10,006人(2024年5月1日時点)
所在地:
・五十嵐キャンパス
〒950-2181 新潟市西区五十嵐2の町8050番地
・旭町キャンパス
医学部医学科
〒951-8510 新潟市中央区旭町通1番町757番地
医学部保健学科
〒951-8518
新潟市中央区旭町通2番町746番地歯学部
〒951-8514
新潟市中央区学校町通2番町5274番地
公式ホームページ:新潟大学
X(旧Twitter):@Niigata_Univ_O
YouTubeチャンネル:Niigata University(official)
新潟大学の学部別偏差値と難易度(レベル)
Benesseの大学受験・進学情報「マナビジョン」のデータによると、新潟大学の偏差値は48~67、大学入学共通テストの得点率は59~84%となっています(2024年12月16日時点)。
学部ごとの偏差値は以下のとおりです。
| 学部 | 偏差値 |
| 人文学部 | 55~59 |
| 教育学部 | 48~53 |
| 法学部 | 53~58 |
| 経済科学部 | 53~59 |
| 理学部 | 52~56 |
| 医学部 | 53~67 |
| 歯学部 | 53~63 |
| 工学部 | 53~54 |
| 農学部 | 53~57 |
| 創生学部 | 54~58 |
参照:新潟大学/偏差値・入試難易度【2024年度入試・2023年進研模試情報最新】|マナビジョン|Benesseの大学受験・進学情報
新潟大学と近い偏差値・難易度(レベル)の大学
ここでは、新潟大学と近い偏差値・難易度(レベル)の大学をいくつかご紹介します。
■偏差値の近い大学「法学部」
香川大学 法学部(偏差値53~54)
岡山大学 法学部(偏差値58)
駒澤大学 法学部(偏差値53~60)
■偏差値の近い大学「教育学部」
島根大学 教育学部(偏差値45~53)
鹿児島大学 教育学部(偏差値45~54)
東北福祉大学 教育学部(偏差値49~54)
■偏差値の近い大学「医学部医学科」
高知大学 医学部医学科(偏差値67)
福井大学 医学部医学科(偏差値67~70)
関西医科大学 医学部医学科(偏差値68~70)
新潟大学入試の特徴
新潟大学は国立大学のため、入試の選抜方法は大学入学共通テストで指定された教科・科目を受験後、個別学力検査を受ける一般選抜が中心です。
このほかには、総合型選抜や学校推薦型選抜などの選抜方法も実施されています。
一般選抜(前期日程・後期日程)
一般選抜には前期日程と後期日程があり、大学入学共通テストと個別学力検査(実技検査・面接・小論文が課される場合もあり)および出願書類によって、合否判定が行われます。
なお、医学部医学科では、前期日程で入学志願者数が募集人員の4倍を上回った場合、2段階選抜が実施されることがあります。
総合型選抜
総合型選抜は次の4学部で実施され、小論文や面接、レポートなどが課されます。
- 経済科学部(大学入学共通テストなし)
- 工学部(大学入学共通テストなし)
- 理学部(大学入学共通テストあり)
- 創生学部(大学入学共通テストあり)
学校推薦型選抜
学校推薦型選抜は、学校長の推薦により出願できる選抜方法です。創生学部以外で実施され、大学入学共通テストが課されない学校推薦型選抜Ⅰ型と、大学入学共通テストが課される学校推薦型選抜Ⅱ型に分けられます。
それぞれ対象となる学部が異なるため、事前によく確認しましょう。
そのほかには、帰国生徒特別選抜や私費外国人留学生特別選抜、社会人特別選抜などがあります。選抜内容の詳細については、最新の募集要項をご確認ください。
また、新潟大学では選抜における学部ごとの採点・評価・合否判定基準が公開されているため、受験を考えている方は確認しておきましょう。
新潟大学の入試科目別の出題範囲とその対策
新潟大学の入試対策のために、試験問題の特徴や傾向をつかんでおきましょう。ここでは、一般選抜(前期日程)での試験問題の特徴をご紹介します。
英語の対策と勉強法
英語は大問が3問で、長文読解が2問、英作文が1問の構成が基本です。基本の試験時間は90分ですが、教育学部学校教員養成課程教科教育コース英語教育専修のみ、大問4のリスニング問題があるため、試験時間が100分になります。
難易度は標準レベルで、長文問題では内容説明や下線部和訳といった内容が中心です。読解力は必要なものの、難問は見られません。
ただし、採点が厳しいといわれているため、記述問題の対策を十分に行い、丁寧な解答を心がけるとよいでしょう。
国語の対策と勉強法
国語は大問が4問で、現代文が2問、古文・漢文が1問ずつの構成です。そのうち、学部ごとに指定された問題を解く形式となっており、試験時間は90分です。
指定の文字数以内で問題文の意味や内容の説明を求めるような問題が多く、すべて解答しようとすると試験時間が足りなくなるおそれがあるため、得意な分野から解き始めるのがおすすめです。
古文・漢文が課せられている場合は、文法や語句を押さえておくと得点を稼ぎやすいため、十分に対策しておくとよいでしょう。
数学の対策と勉強法
数学は、人文学部・教育学部・経済科学部・農学部・創生学部の5学部と、理学部・医学部・歯学部・工学部の4学部で問題用紙が異なり、大問数も変わります。
前者は大問4問、後者は大問6問で構成されており、後者は6問の中で学部ごとに指定された問題を解く形式です。試験時間は90分または120分です。
前者5学部の難易度は標準からやや難レベル、後者4学部の難易度はやや難レベルですが、近年の傾向では難度が高まってきています。
あらゆる分野から出題されますが、頻出分野となるのがベクトルや微分積分です。
過去問を使って演習を進める場合は、新潟大学のものだけでなく他大学のものも利用することをおすすめします。時間配分を意識しながら十分に演習を積み、苦手分野をなくしておきましょう。
新潟大学試験の概要

ここからは、新潟大学試験の概要を解説します。
出願資格について
新潟大学の出願資格は、選抜方法ごとに定められています。ここでは、一般選抜での出願資格をご紹介します。
一般選抜では、大学入学共通テストで指定の教科・科目を受験したうえで、以下のいずれかに該当する場合に出願が可能です。
(1)高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ。)を卒業した者及び入学年の3月卒業見込みの者
(2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び入学年の3月修了見込みの者
(3)高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる次の①から⑥のいずれかに該当する者及び入学年の3月31日までにこれらに該当する見込みの者
①外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
②文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するものとして認定又は指定した在外教育施設の当該課程を修了した者
③専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
④文部科学大臣の指定した者
⑤高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程
度認定試験に合格した者(廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
⑥本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの
なお、上記の⑥に該当する場合には、個別の入学資格審査が行われます。詳細は受験生特設サイトをご覧ください。
入試日と出願の受付期限
入試日と出願期間は、選抜方法によって異なります。ここでは、2025年度の一般選抜の日程をご紹介します。
| 区分 | 出願期間 | 試験日 |
| 一般選抜(前期日程) | 2025年1月27日(月)~2月5日(水) | 2025年2月25日(火) 2025年2月26日(水) 2025年2月27日(木) (学部により異なる) |
| 一般選抜(後期日程) | 2025年3月12日(水) |
新潟大学への出願は、インターネット出願サイトに出願登録後、出願期間内に必着で提出書類を郵送します。スケジュールに余裕を持って準備を進めましょう。
入試科目や配点
ここからは、新潟大学の試験科目や配点をご紹介します。今回取り上げるのは、人文学部・医学部(医学科)の内容です。そのほかの学部・学科の試験内容については、最新の募集要項にてご確認ください。
なお、以下のデータはすべて2024年11月27日現在のものです。
人文学部
| 教科・科目名(大学入学共通テスト) | 配点 | |
| 国語 | 『国語』 | 100 |
| 数学 | 『数学Ⅰ,数学A』『数学Ⅰ』から1科目選択 『数学Ⅱ,数学B,数学C』必須 | 100 |
| 理科 | 『物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎(2出題範囲を選択)』『物理』『化学』『生物』『地学』から1科目選択 | 50 |
| 外国語 | 『英語』『ドイツ語』『フランス語』『中国語』『韓国語』から1科目選択 | 100 |
| 地歴 | ①『地理総合,地理探究』『歴史総合,日本史探究』『歴史総合,世界史探究』から1科目選択 | 100 |
| 地歴・公民 | ②『地理総合,地理探究』『歴史総合,日本史探究』『歴史総合,世界史探究』『地理総合/歴史総合/公共(2出題範囲を選択)』『公共,倫理』『公共,政治・経済』から1科目選択 ※②の選択は①で選択した科目以外から行い、②で『地理総合/歴史総合/公共』を選択する場合は、①で選択した科目と同一名称を含む出題範囲は選択できない | |
| 情報 | 『情報Ⅰ』 | 50 |
| 合計 | 500 | |
| 教科・科目名(個別学力検査) | 配点 | ||
| 国語 | 現代の国語、言語文化、論理国語、古典探究 | 200 | |
| 外国語 | 英語(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ)、ドイツ語、フランス語から1科目選択 | 200 | |
| 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B、数学C | 左記から1科目選択 | 100 |
| 地歴 | 世界史(歴史総合・世界史探究)、日本史(歴史総合・日本史探究)、地理(地理総合・地理探究) | ||
| 合計 | 500 | ||
医学部(医学科)
| 教科・科目名(大学入学共通テスト) | 配点 | |
| 国語 | 『国語』 | 100 |
| 数学 | 『数学Ⅰ,数学A』『数学Ⅱ,数学B,数学C』 | 200 |
| 理科 | 『物理』『化学』『生物』から2科目選択 | 200 |
| 外国語 | 『英語』『ドイツ語』『フランス語』から1科目選択 | 200 |
| 地歴・公民 | 『地理総合,地理探究』『歴史総合,日本史探究』『歴史総合,世界史探究』『地理総合/歴史総合/公共(2出題範囲を選択)』『公共,倫理』『公共,政治・経済』から1科目選択 | 50 |
| 情報 | 『情報Ⅰ』 | 50 |
| 合計 | 800 | |
| 教科・科目名(個別学力検査等) | 配点 | ||
| 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学A、数学B、数学C | 400 | |
| 理科 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2科目選択 | 400 | |
| 外国語 | 英語(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ) | 400 | |
| その他 | 面接 | – | |
| 合計 | 1,200 | ||
出願者数や合格者数のデータ
新潟大学の出願者数や合格者数は以下のとおりです。なお、ここで取り上げるのは2024年度一般選抜(前期日程)の結果です。
| 学部(学科) | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
| 人文学部 | 271 | 243 | 156 | 1.6 |
| 教育学部 | 332 | 283 | 137 | 2.1 |
| 法学部 | 161 | 152 | 98 | 1.6 |
| 経済科学部 | 400 | 383 | 214 | 1.8 |
| 理学部 | 279 | 258 | 157 | 1.6 |
| 医学部 | 582 | 471 | 172 | 2.7 |
| 歯学部 | 144 | 115 | 41 | 2.8 |
| 工学部 | 577 | 528 | 353 | 1.5 |
| 農学部 | 227 | 207 | 126 | 1.6 |
| 創生学部 | 173 | 145 | 50 | 2.9 |
新潟大学の受験料と学費目安度
新潟大学の入学検定料は17,000円、大学入学共通テストの検定料は18,000円(3教科以上受験の場合)です。
入学料は282,000円、年間の授業料は535,800円で、そのほかに各種保険料として以下の費用が必要になります。
- 学生教育研究災害傷害保険:3,300円または4,700円
- 学生教育研究賠償責任保険:1,360円
- 学研災付帯学生生活総合保険:36,790円~91,330円
新潟大学卒業後の進路
新潟大学の2023年度卒業生の進路状況は、以下のとおりです。
| 学部名 | 卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | 就職率 |
| 人文学部 | 224 | 180 | 19 | 95.7% |
| 教育学部 | 186 | 159 | 16 | 100.0% |
| 法学部 | 176 | 154 | 8 | 97.5% |
| 経済科学部 | 321 | 288 | 10 | 98.0% |
| 経済学部 | 25 | 16 | 0 | 72.7% |
| 理学部 | 199 | 79 | 109 | 100.0% |
| 医学部 | 284 | 250 | 22 | 100.0% |
| 歯学部 | 60 | 53 | 2 | 100.0% |
| 工学部 | 548 | 186 | 350 | 99.5% |
| 農学部 | 178 | 83 | 85 | 97.6% |
| 創生学部 | 63 | 58 | 2 | 100.0% |
| 合計 | 2,264 | 1,506 | 623 | 98.2% |
※就職率は、就職希望者に対する就職者の割合を示しています。
学部別の就職率は、教育学部・理学部・医学部・歯学部・創生学部で100%、人文学部・法学部・経済科学部・工学部・農学部で95%以上と、全体的に高い水準であることがわかります。
また、進路の内訳を見ると、文系学部では公務員への就職率が24.6%、教員への就職率が14.2%と高い割合であるのが特徴です。
理系学部では6割以上が進学を選択し、その多くが新潟大学大学院やほかの国立大大学院などへと進学しています。
参照:新潟大学 キャリア・就職支援オフィス:新潟大学の進路・令和5年度職業・産業別就職状況および進学状況
新潟大学が気になった人はオープンキャンパスや入試説明会へ
新潟大学のオープンキャンパスは、全学部を対象に対面形式とオンライン形式、オンデマンド形式で実施されています。2024年度は、8月8日(木)~9日(金)の2日間で開催されました。
対面形式とオンライン形式の参加には事前の申し込みが必要ですが、「オープンキャンパス特設サイト」から視聴できるオンデマンド形式のものは予約不要で視聴できます。
新潟大学オープンキャンパスでは、主に高校生向けのイベントが開催されており、学部ごとに全体説明会や模擬講義、個別相談会などのプログラムが用意されています。
事前申し込みが必要なイベント・プログラムもありますが、キャンパス内見学のみの場合、予約などは不要です。
新潟大学に合格するための勉強方法

ここからは、新潟大学に合格するための勉強方法をご紹介します。
新潟大学に入るにはどのような対策をすればいい?
新潟大学は、いわゆる「5S大学※」の1校で、国立大学の中でも上位レベルの準難関校という位置付けです。
※新潟大学・埼玉大学・静岡大学・信州大学・滋賀大学
また、新潟大学は歴史が深く、医学部も擁することから、旧帝大に次ぐ人気があるといわれています。
受験する場合は、準難関校であることをふまえて、大学入学共通テスト・個別学力検査の十分な対策を行いましょう。
その際は、自分の志望する学部・学科で求められる学力レベルを過去問などから把握し、範囲を絞り込んで勉強していくのがおすすめです。
1つのミスが合否を分ける可能性もあるため、ミスなく解答できる解答力を身につけておきましょう。
さらに、新潟大学は採点が厳しい教科があるといわれています。大学入学共通テストを含め、基礎を徹底することはもちろん、スピーディーかつ丁寧に解くようにしましょう。
受験期の過ごし方と勉強のコツ
受験期の高校3年生をどのように過ごすかにより、合否の確率が変わってきます。やみくもに勉強するのではなく、年間を通したスケジュールを立てて、計画的に取り組みましょう。
- 春(4~5月):基礎学力を定着させる時期です。教科書の内容に沿って丁寧に学習し、苦手分野を洗い出しておきます。単語集や用語集を使った暗記ものは、早めに学習を始めておきましょう。
- 夏(6~8月):春に洗い出した苦手分野を克服する時期です。長期休暇中はまとまった時間を勉強に充てやすいため、学力を底上げして成績アップを狙いましょう。「週に問題集を○ページ進める」など、小さな目標を繰り返し達成できると、モチベーションを維持しやすいでしょう。
- 秋(9~11月):大学入学共通テストの対策を始める時期です。問題演習を繰り返す中で間違えた箇所があれば、間違えた原因や対処法をしっかりと考えましょう。
- 冬(12月~):本番に向けて過去問を集中的に学習し、演習を積む時期です。個別学力検査対策では、志望校の傾向をつかむだけでなく、時間配分に気を付けてミスなく問題を解くようにして最後の仕上げをしましょう。
新潟大学を目指すなら予備校を使って入試対策をしよう
独学で受験勉強に取り組む場合、志望する学部・学科にもよりますが、継続する意志と情報収集力がないと厳しい戦いになってしまいます。
限られた期間で効率的に入試対策を進めたい方は、プロの講師から指導を受けられる予備校を利用するのがおすすめです。予備校を利用すれば、志望校合格に向けて適切な指導を受けられるだけでなく、大学入試に関する最新情報を得ることもできます。
しかし「予備校に通っていれば安心」とも言い切れません。大手予備校の場合、一度に多くの生徒が同じ授業を受けるのが一般的です。
大人数の授業では、講師の話を受け身で聞いて理解できたと錯覚しているだけの場合があり、受験に必要な力が定着しないおそれがあります。
また、集団授業の中で、苦手分野が取り残されることもあるでしょう。授業でわからなかった部分は自分から講師に聞きに行くなど積極的に取り組まないと、学習の効果が出ないかもしれません。
大学受験へ向けて予備校を探したい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
予備校に通っているのに成績が伸びない理由は?なぜか模試A判定がでない4つの理由
四谷学院のカリキュラムのご案内
予備校の授業に起こりがちな欠点をカバーしてくれるのが、四谷学院の「ダブル教育」です。
ここからは、ダブル教育で取り入れている「科目別能力別授業」「55段階個別指導」について解説します。
科目別能力別授業
多くの予備校では、志望校や入塾テストの総合得点でクラス分けが行われます。そのため、授業についていけない、得意科目の授業が物足りないといった「科目ごとのレベルの不一致」が起こりがちです。
四谷学院の科目別能力別授業では、そのようなレベルの不一致が起きないように、科目と能力の2つでクラスを分けているのが特徴です。つまり、科目ごとに自分に合ったレベルの授業が受けられる仕組みになっています。
自分のレベルに合った授業を受ければ、より効率的に成績向上を目指せます。
55段階個別指導
科目別能力別授業で得た理解力を、解答力につなげるのが55段階個別指導です。
55段階個別指導では、過去の入試問題を徹底的に分析して作られた記述式の55テストを用いて、理解できていない部分や不完全な部分、表現が不適切な部分などを段階的にチェックしていきます。
解答力が身についているかどうか確認しながら級を進めることで、中学レベルから志望校合格レベルまでの55段階を無駄なく学べるシステムです。
新潟大学に合格するには丁寧な解答が重要!
【新潟大学の入試概要】
- 大学入学共通テストと個別学力検査を受ける一般選抜が中心
- 総合型選抜や学校推薦型選抜などもある
- 難易度は標準~やや難
【新潟大学の入試データまとめ】
- 一般選抜(前期日程)の実質倍率は1.5~2.9倍(2024年度試験)
【勉強方法まとめ】
- 素早く丁寧な解答ができるよう基礎を十分に身につけ、教科書や用語集、過去問などを活用し学習する
- 記述を求める問題が多く時間が足りなくなる科目もあるため、時間配分の練習をしておく
新潟大学は、難易度がやや平易からやや難レベルと学部によって差がありますが、歴史ある国立大学で人気も高く、ハイレベルな戦いになりやすいことが予想されます。したがって、基礎を徹底したうえで、いかにミスを少なくして問題を解くかが重要になります。
そこでおすすめなのが、四谷学院の「ダブル教育」です。自分の学習レベルに合った授業で、無理なく効率的な成績向上が望めるため、志望校合格への近道となります。気になる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※本記事でご紹介した情報は2024年11月27日現在のものです。最新の情報は大学公式ホームページにて必ずご確認ください。
失敗しない予備校選びは説明会・相談会参加が重要!
大学受験を成功させるには、自分の学習スタイルや学力に合った予備校を選ぶことが大切です。パンフレットやインターネットだけでは得られる情報に限りがあるため、説明会・相談会に参加することをおすすめします。
予備校の説明会・相談会では、学習環境や授業風景を確認できるため、自分が通うイメージを持ちやすいでしょう。自分の目で確かめたうえで「ここで頑張りたい」と思える予備校を選ぶと、失敗が少なくなります。
以下の記事では、説明会・相談会に参加する際に確認したい予備校のチェックポイントや、参加時の不安を解消する方法などを解説しています。