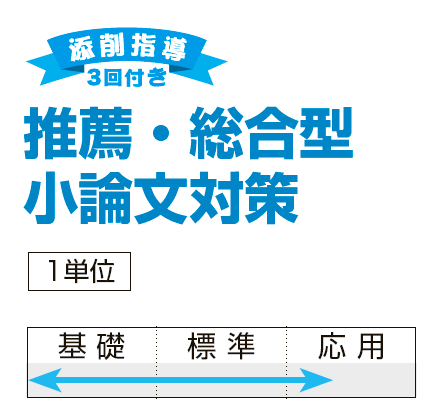こんにちは、四谷学院の受験コンサルタント田中です。
大学入試は、高校入試以上にさまざまな選抜方法があり、これまでは「一般選抜」が主流でした。しかし、近年は「学校推薦型選抜」や「総合型選抜」で受験する方が増加傾向にあります。
そのため、「推薦で合格を目指したい」と考える高校生も多いのではないでしょうか。
文部科学省の発表によると、2025年度入試における国公立大学の実施率は以下のとおりです。
- 学校推薦型選抜:96.6%
- 総合型選抜:69.8%
そこで本記事では「学校推薦型選抜」の中でも、特に「指定校推薦」について詳しく解説します。
目次 [非表示]
学校推薦型選抜とは
従来の「推薦入試」は、2021年度入学者向けの大学入試より「学校推薦型選抜」に名称が変更されました。「学校推薦型選抜」は、評価方法によって次の3種類に分けられます。
- 公募制一般推薦
- 公募制特別推薦
- 指定校推薦
公募制一般推薦
公募制一般推薦とは、各大学が定める基準を満たし、かつ在学高校(学校長)から推薦を得ることで受験できる推薦方法です。
この推薦方法では、大学の学科ごとに設定された基準をクリアし、募集要項の記載条件を満たす必要があります。ただし、在学高校の推薦を受けられれば、どの高校からでも出願可能です。
なお、公募制一般推薦で求められる評定平均は4.0程度となります。
評定平均に関して、詳しくは「【学校推薦型選抜】評定平均とは?内申点を上げるための対策を解説します!推薦入試対策をしよう」を併せてご覧ください。
公募制特別推薦
公募制特別推薦とは、スポーツや文化活動、資格、検定などで優れた成績を残した方が利用できる推薦方法です。
出願条件は大学によって異なりますが、公募制一般推薦と異なり評定平均の基準が設けられることはほとんどありません。
なお、出願には公募制一般推薦と同様、在学高校からの推薦が必要です。
指定校推薦
指定校推薦とは、大学が指定した高校の生徒が応募できる推薦方法のことです。
大学は、推薦を受ける高校を以下の基準で選定します。
- その高校の前年度までの一般入試結果
- 過去に指定校推薦で合格した生徒の大学での成果
もし、指定校推薦の受験者が入学辞退や入学後すぐに退学した場合、翌年以降に出身高校で推薦枠の取消しや指定校枠の減少となる可能性があります。
指定校推薦は、大学と高校の信頼関係によって成り立っている制度であり、毎年必ず推薦枠が確保されるわけではありません。例えば「昨年は指定校枠があったけれど、今年からその枠がなくなる」といったケースもある点に注意が必要です。
学校推薦型選抜と総合型選抜の違い
学校推薦型選抜は、在学高校から推薦を受けて出願するのに対し、総合型選抜は自己推薦で出願します。
なお、総合型選抜では、大学が求める人物像(アドミッション・ポリシー)により近い人物を選抜するため、大学や学部ごとにさまざまな評価方法が用いられます。
試験方法は大学や学部によって異なるため、募集要項をよく確認しましょう。
出願時期のピークは、学校推薦型選抜が11月~12月、総合型選抜は9月~11月頃です。出願時期に2ヵ月ほどの差があり、合格発表のタイミングも異なります。
学校推薦型選抜と総合型選抜の違い
| 学校推薦型選抜 | 総合型選抜 | |
| 推薦 | 在学高校 | 自分 |
| 出願時期 | 11月~ | 9月~ |
| 合格発表時期 | 12月~ | 11月~ |
指定校推薦と公募推薦の合格率

次に、指定校推薦と公募推薦の合格率の違いをご紹介します。
指定校推薦の合格率
指定校推薦は、主に私立大学で採用されており、大学は高校ごとに推薦枠を設定します。
ただし、推薦枠は通常1つの高校に数名しか割り当てられません。人気の高い大学の指定校枠を巡っては、推薦者を決める学内選抜が行われる場合もあります。
指定校推薦は、高校と大学との信頼関係から成り立つ制度です。高校内の選考を勝ち抜けばほぼ確実に合格できるでしょう。早い段階での合格が期待できるという安心感から、人気の高い入試制度となっています。
公募推薦の合格率
公募推薦には「推薦」の名称が付きますが、出願資格を満たしていれば誰でも受験できる選抜方法であり、合格が保証されるわけではありません。
合格率は、国公立大学や上位の大学で20~40%、中堅以下の大学で約60%といわれています。
指定校推薦がほぼ確実に合格できる一方で、公募推薦は同じ推薦型でも合格率に大きな差がある点に注意しましょう。
指定校推薦の選考方法

指定校推薦では、書類審査とそのほかの試験を通じて選考が行われます。ここからは、指定校推薦の選考方法をご紹介します。
書類審査
指定校推薦は一般選抜と異なり、高校在学中の学業成績(評定平均)や課外活動(部活・ボランティア活動など)といった日頃の努力が評価される点が特徴です。
学校成績だけでなく、部活動やスポーツ、文化活動などに関する推薦基準が設けられており、大学が提示した基準を満たしている生徒を高校(学校長)が推薦します。
書類審査
- 学業成績(評定平均)
- 調査書
- 推薦書
- 資格や検定 など
それ以外の試験
書類だけではわからない部分への注目度が高いのが、指定校推薦の特徴の一つです。小論文や面接、プレゼンテーション等によって受験生の思考力・人柄・個性を評価します。
それ以外の試験
- 小論文
- プレゼンテーション
- 口頭試問
- 実技
- 大学入学共通テスト など
指定校推薦を勝ち取るためのコツ
指定校推薦の募集枠は、一般的に各高校1人~3人程度であり、出願条件も厳しいものが多くなっています。
指定校推薦枠を勝ち取るには定期テストでよい点数を取るだけでなく、部活動で優秀な成績を収めるなどして、評定平均を上げることがポイントです。
また、高校3年間の評定平均は、定期テストの回数を考慮すると、2年生が終わる段階で平均の8割が決まる計算になります。
そのため、高校1年生のうちから評定平均を上げる努力をすることが大切です。
高校3年生になってから頑張ろうとしても、早い段階で評定平均アップを目指して努力しているライバルには太刀打ちできないケースもあるでしょう。
勉強に不安がある場合は、塾や予備校を利用して苦手科目や苦手意識を克服するのも有効です。
指定校推薦の試験でみられる内容は?
指定校推薦では一般的に学科試験は行わず、面接や論文、志望動機の提出などが求められます。
ここからは、指定校推薦の対策方法をみていきましょう。
志望動機の書き方
指定校推薦では、総合型選抜で求められる志望理由書に比べて、簡易的な志望動機の提出を求められるのが一般的です。
受験する大学の特色やアドミッション・ポリシーをよく理解し、以下のポイントを押さえて志望動機を作成しましょう。
- その大学に行きたい理由
- その学部・学科を志望した理由
- その学部・学科で何をしたいのか
面接対策
指定校推薦の面接では、学力以外に以下のようなポイントが評価されます。
- 思考力
- 人柄
- 個性
- 進学意欲 など
面接形式は個人面接以外にも、集団面接やグループディスカッション、プレゼンテーションなどを採用する大学もあるため、事前に確認し、練習や模擬面接を行いましょう。
質問に対する回答では、大学が求める人物像に合った内容をアピールすることが大切です。
大学入試の面接でよく聞かれる質問には、以下のようなものが挙げられます。
- 志望動機に関する質問
- 大学入学後の展望に関する質問
- 大学卒業後の進路に関する質問
- 自分自身に関する質問
- ニュースや時事問題に関する質問
- 逆質問 など
このほか、自己推薦書の内容を深掘りされることもあるため、いつでも見返せるよう自己推薦書のコピーを持参しておくと安心です。
論文対策
小論文は、大学が指定するテーマに対して自分なりの仮説と論拠を述べるものです。
小論文には、事前に作成したものを提出するパターンと、入試当日に書くパターンがあります。どちらの選考方法かは、事前に確認しておきましょう。
出題されるテーマは大学により異なりますが、学部や学科、志望動機に関するテーマが一般的です。
志望校の傾向を把握したうえで、さまざまなテーマに慣れ、学校や予備校の先生に添削を受けながら完成度を高めていきましょう。
小論文対策では、むやみに回数を重ねるのではなく、以下のポイントを押さえることが大切です。
- 書きたい内容をメモにまとめ、大枠を決めてから書き出す
- 試験時間内に書き上げられるよう、時間配分を意識して練習する
- 志望校の指定校推薦における小論文試験の傾向を必ず確認する
- 最低でも10テーマを目標に練習し、直すべき癖を見つける
その他
大学によっては、論理的な思考力やプレゼンテーション能力を評価するため、プレゼンテーションや口頭試問が実施される場合があります。
口頭試問は、明確な解答を求められる設問が出されることもあり、解答に至るプロセスが重視されます。
志望校の指定校推薦に「プレゼンテーション」や「口頭試問」が含まれている場合は、志望校の出題傾向を調べて個別に対策を立てましょう。
口頭試問対策については、「大学入試の口頭試問の攻略法解説!面接との違いや対策も解説」で詳しく解説しています。
指定校推薦の選考スケジュール

学校推薦型選抜は、一般選抜よりも早く実施されます。
校内選考がある場合、選考は9月頃からスタートし、大学への出願は11月頃、合格発表は12月頃です。
受験スケジュールのピークは11月~12月ですが、試験の時期は大学や学部・学科によって異なります。
※なお、大学入学共通テストを受ける場合は、1月に実施されます。
指定校推薦で求められる評定
指定校推薦で求められる評定平均は大学により異なりますが、最低でも「3.5以上」、一般的には「4.0以上」が目安です。
ただし、実際には大学の出願条件で定められている評定平均をキープしている在校生を対象に校内選考が行われます。そのため、出願条件よりも高い評定平均が求められるケースも珍しくありません。
難関私立高校の指定校推薦枠を獲得し、校内選考を有利に突破したい場合は、最低でも評定平均「4.5以上」を目指しましょう。
指定校推薦の受験対策の注意点

指定校推薦では、早い段階から学校の成績を上げることが重要です。志望大学を決めたら、定期試験の成績を上げて出願に必要な評定平均の基準をクリアすることが最低条件となります。
さらに、出願書類の作成や面接対策など、一般選抜の受験よりもかなり早くから準備を始める必要があります。
指定校推薦の合格率はほぼ100%ですが、校内選考がある場合は、併願大学の検討も忘れずに行いましょう。
万一、不合格となった場合に備えて、一般選抜に切り替えられる準備をしておくことも大切です。
基礎学力が合否を握る
指定校推薦でも一般選抜でも「基礎学力」が非常に重要です。
四谷学院で学力の土台を作り、高1・高2の学校成績を向上させましょう!
まとめ
学校推薦型選抜は、主に「公募推薦」と「指定校推薦」があります。指定校推薦は、在学高校(学校長)からの推薦があれば、ほぼ確実に志望校に合格できる選抜方法です。
指定校推薦の枠は高校ごとに限られており、校内選考を勝ち取るには高校1年生から大学受験を視野に入れて成績アップを目指すことが重要です。
高い評定平均を維持していれば、ライバルより有利な条件で指定校推薦を受けられます。
高校の勉強に不安がある方、定期テストの結果に自信がない方は、効率よく勉強を進めるためにも塾や予備校の利用を検討しましょう。
失敗しない予備校選びは相談会・説明会参加が重要!
予備校を選ぶ際は、自分に合った環境かどうかを慎重に比較することが大切です。合わない塾や予備校に通うと、期待する成果や成績を得られない場合があります。
予備校選びでは口コミやWebサイトの情報だけでなく、実際に相談会や説明会に参加し、学習環境や指導方針、サポート体制などを確認することが大切です。
複数の予備校を訪れて比較検討すれば、自分に合う予備校がきっと見つかるはずです。
予備校の説明会で確認すべきポイントについては、「大学受験予備校「説明会」の参加の仕方と確認ポイント」を併せてご覧ください。